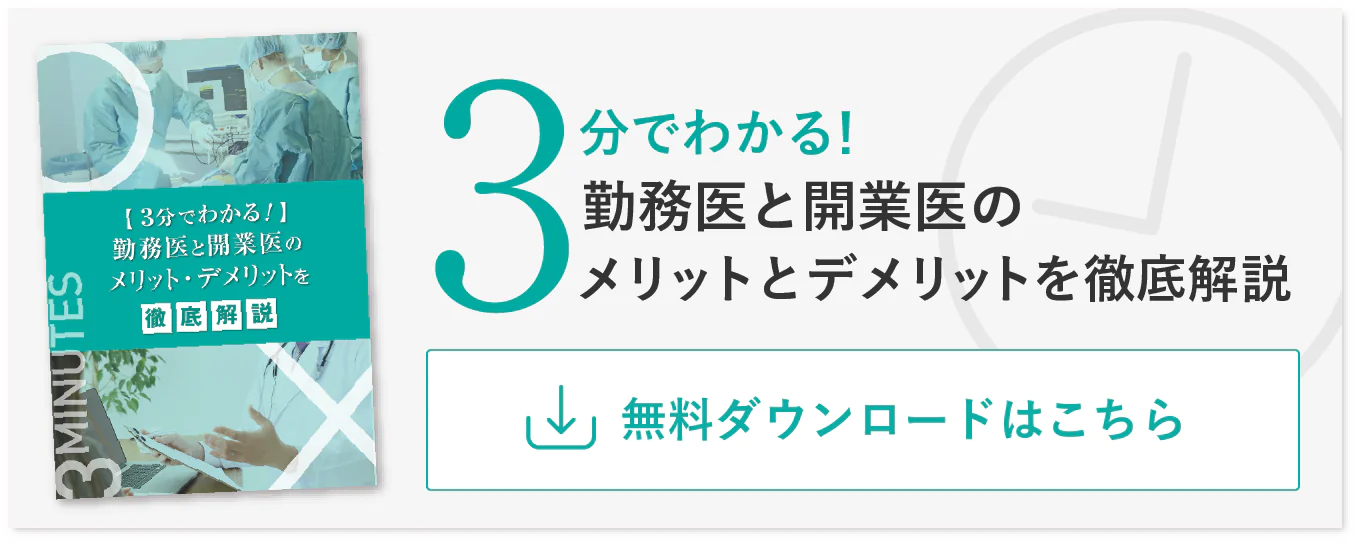医師の離婚の慰謝料|相場はどれくらい?どんなときに請求できる?


3人に1人が離婚すると言われる時代と言われて長いですが、開業医・勤務医の先生問わず医師の離婚率も同じくらいと言われています。
多忙やストレスを理由にすれ違いが起こることも多く、離婚に至ることは決して珍しくありません。
離婚の際に問題になることの1つが、お金の問題です。離婚の際に発生するお金の問題は様々ありますが、今回は慰謝料について、主に詳しくお伝えしていいきます。
混同しやすい離婚のお金の問題
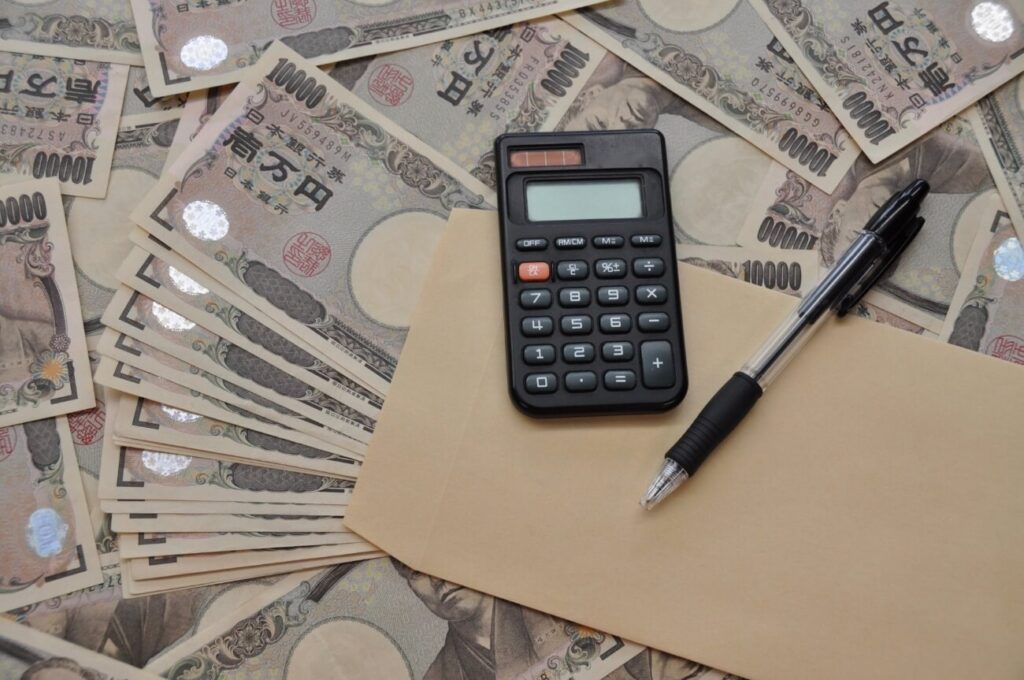
弁護士の先生とお話をすると、離婚相談の際に必ず聞かれるのが、「慰謝料はどれくらいになりますか?」という質問だそうです。
しかし、慰謝料に対して問い合わせする人の大半は、財産分与や養育費、婚姻費用と混同しているケースが多いと言います。
慰謝料と財産分与、養育費や婚姻費用は別々に考える必要があります。民法でも明確に区別されています。
そこでまずは、離婚の際に発生するお金の問題について整理します。
養育費
養育費は、未成年の子供が社会自立をするまでに必要とされる、将来に渡って払っていく費用です。(民法752条、877条)
未成年の子供がいる状態で離婚すると、子供の親権・監護権を夫か妻のどちらかが持つことになります(通常は妻が親権・監護権を持つことが多い)。
子供を監護する親は、子供を監護していない親に対して、子供を育てていくために必要な費用を請求することができます。
婚姻費
民法760条では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」としています。これが婚姻費用です。
具体的には、夫婦生活で必要な居住費や生活費、子供の学費といった費用です。
例えお互いが憎み合っていても、離婚調停中であっても、法律上はまだ夫婦です。
つまり民法に従えば、このような場合でもお互いに生活を助け合う義務があるのです。
仮に、別居中の相手が「生活費を入れてくれない」といった場合には、生活費を請求する権利があります。これが婚姻費用分担請求です。
財産分与
財産分与は、「結婚している間に夫婦で築いた財産を、原則として分ける」ことです。(民法768条)
貯金だけでなく、保険や有価証券、そして夫婦で購入した家や車などの固定資産も対象になります。
貢献度に応じて分配する通常の財産分与を清算的財産分与の他、離婚後に生活が困窮する配偶者を扶養する扶養的財産分与があります。
また慰謝料と財産分与は裁判では別々に考えますが、不倫等で離婚に至ったにも関わらず、相手が慰謝料の支払いを拒む場合があります。
その場合に慰謝料的な意味合いで、原因を作った方が、相手に貢献度以上の財産を分け与える慰謝料的財産分与という考え方があります。
慰謝料
慰謝料は、財産分与と同様、現在の財産の中から決められるお金なので、比較的財産分与と混同されやすいでしょう。
慰謝料的財産分与という似たようなものはありますが、基本的には慰謝料と財産分与は別々で考えます。
財産分与は「結婚している間に築いた財産はお互いに納得する割合で分けましょう」というものです。
一方で慰謝料は、基本的に悪いこと(不法行為)をしたら、それに対して相手に賠償するお金です。
慰謝料については民法709条、710条、不法行為が原因となる離婚については民法770条で定められています。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法709条 不法行為による損害賠償
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
引用元:民法710条 財産以外の損害の賠償
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
引用元:民法770条 裁判上の離婚
なお、民法770条には離婚について書かれていますが、離婚しないような場合でも上記の不法行為があれば慰謝料の請求はできます。(多くは離婚に至ると思われますが)
ここではっきりすることは、不法行為以外の原因の離婚については慰謝料を請求できないことです。
「離婚すれば必ず慰謝料が発生する」ということでは決してなく、むしろ慰謝料を請求できるケースは割合的には少ないでしょう。
離婚に関するお金のまとめ
離婚に伴うお金については、以上の4種類です。それぞれ混同されやすいですが、民法でも明確に区分されているのがわかります。
以下に、離婚に関するお金についてまとめます。
| 養育費 | 離婚後~子供の自立までに継続的に支払う費用 | 民法766条、877条 |
|---|---|---|
| 婚姻費 | 結婚~離婚までの間に必要な生活費、居住費、子供の学費等。別居していても請求は可能。 | 民法760条 |
| 財産分与 | 結婚している間に夫婦で築いた離婚時点での財産を、各々の貢献度に応じて2人で分ける | 民法768条 |
| 慰謝料 | 不法行為をしたら、相手に賠償する費用 | 民法709条、710条770条 |
時系列で言えば、離婚時点の財産の中から支払うお金が慰謝料や財産分与、離婚前に発生するのが婚姻費、離婚後は養育費ということになります。
離婚の慰謝料はどんな場合に請求できるのか?

ここまでで離婚時の慰謝料は、相手方に不法行為があった場合に請求できる費用であることがわかりました。具体的にどのような場合に慰謝料を請求できるのでしょうか?
慰謝料を請求できる場合

慰謝料を請求する際、基準となるのが相手方の違法性です。
あくまで慰謝料は不法行為によって発生する費用ですから、相手方の行為に明らかな違法性がなければ請求できません。
つまり「精神的苦痛を受けて、もう耐えられない」だけでは十分ではなく、離婚原因に違法性があり、なおかつ証拠が求められます。
慰謝料が請求できる「明らかな違法性」とは、上記の民法709条、710条、770条を読み解くと、次のようなものになります。
・浮気や不倫などの不貞行為があった
・相手から暴力や暴言(DV)を受けていた
・相手が子供に虐待を加えていた
・生活費を渡さないなど、悪意の遺棄があった
・通常の性的交渉を一方的に拒否された
民法にも書いてある「不貞行為」「悪意の遺棄」は、いずれも民法770条で出てくる言葉です。
不貞行為:自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと
悪意の遺棄:正当な理由なく、同居して助け合いながら生活するという義務を果たさない(民法752条)
「悪意の遺棄」とは、具体的には、次のような行為です。
・相手が生活費を入れてくれない
・相手が不倫相手と一緒に住んで家に帰ってこない(不貞行為も慰謝料の要因)
・相手が「姑と暮らしたくない」と言って、実家に帰ったまま
・健康なのに相手が働こうとしない
・専業主婦の妻が家事をしない
・共働きなのに夫が家事を分担しない
慰謝料を請求できない場合

一方で、慰謝料の請求が認められないようなケースは次の通りです。
・相手に離婚原因の責任がない
・両方が不倫していたなど、夫婦それぞれに離婚原因がある
・不仲や性格の不一致
・不倫をする前から夫婦関係が破綻していた
・不倫相手からの慰謝料支払いなどにより、すでに損害が補填されている場合
単に「結婚生活が進むにつれて仲が悪くなった」「相手がキモい、どん引きする」くらいでは、ほぼ100%慰謝料は請求できません。
また、夫と妻が両方不倫しているというのは、ドラマではよく見るシーンですが、こちらも慰謝料を請求することは不可能です。
不倫前から夫婦関係が冷え切った状態など明らかに破綻していれば、不倫を理由とした離婚には当たらないため、慰謝料は請求できません。
このように離婚の慰謝料は、ドロドロした複雑な感情だけでは判断できず、原因を論理的に分析することが必要です。
「不倫→離婚→慰謝料」という図式が必ずしも成り立つわけではないので注意しましょう。
慰謝料の時効

離婚の慰謝料についても時効が存在します。
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。引用元:民法724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
事実と加害者を知った日から3年間
不倫を例にすると、民法第724条第1項は、不倫の事実と不倫相手を把握してから3年間が時効ということになります。
3年を過ぎると、不倫相手に対する慰謝料請求ができなくなります。
しかし、民法第159条より、配偶者に対しての不倫の慰謝料に関しては、離婚が成立したあと6ヶ月経たないと時効が成立しません。
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
引用元:民法第159条 夫婦間の権利の時効の完成猶予
事実があってから20年間
民法第724条から、事実が発生してから20年経つと時効が成立します。この場合は、事実を認識していたかどうかに関わらずに時効が進みます。
不倫であれば、不倫があった日から20年後に、不倫の事実を知らなくても時効が成立することになります。
なお、2020年の民法改正前については、この部分は「時効」ではなく「除斥期間」でした。
除斥期間と時効の違いとは、以下のようなものです。
| 除斥期間 | 時効 | |
|---|---|---|
| 一定期間権利を行使しないことで権利が自動的に消滅し、期間が延長されることはない。 | 一定期間権利を行使しないことに加え、当時者によって時効援用があって権利が消滅する。訴訟提起を行えば時効を中断し、期間が延長される。 | |
| 中断 | × | 〇 |
| 停止 | × | 〇 |
| 時効援用 | × | 〇 |
つまり、民法改正前は20年経過した時点で権利が消滅してしまいますが、時効では、権利の経過を停止することができます。
除斥期間より時効の方が有利に進めることができるということになります。
しかし、2020年3月31日時点で不貞行為などから20年が経過していれば、除斥期間の方が適用されて慰謝料は請求できません。
逮捕を理由に離婚する場合は慰謝料を請求できるか?

よく芸能人や著名人が逮捕されると、その後離婚したと報道されることがあります。
このように、自分や子供に直接的な被害はなくても、相手の犯罪行為により離婚に至ることもあるでしょう。
その場合は慰謝料を請求できるのでしょうか?
結論から述べると、必ずしも慰謝料を請求できるとは限りません。
慰謝料を請求できたとしても、逮捕されたことを理由として増額できるとも限りません。
明らかな違法行為ではありますが、離婚とは関係のない犯罪行為で逮捕された可能性があるためです。
逮捕理由が結婚生活と十分関係あるものでなければ、慰謝料を請求することは厳しいです。
「世間体が気になる」「逮捕によって自分も恥をかかされる」と言う理由だけでは慰謝料の請求は厳しいでしょう。
しかし、結婚生活を継続しがたい重大な理由があれば話は別です。慰謝料を請求できる可能性は十分ありますし、増額もできます。
配偶者の逮捕が原因で経済的・精神的な損害を被ったと感じた場合は、慰謝料を請求するべきでしょう。
医師の離婚の慰謝料の相場はどれくらいか?

一般的に離婚の慰謝料の相場は100~300万円と言われていますが、あくまでこれまでの判例をもとに言われている数字です。
また、離婚理由によって慰謝料の額はケースバイケースであり、一概には言えず明確な判断が難しいのが現状です。
また、医師は年収が高いので、慰謝料の相場は一般より高いと言われることもありますが、果たしてそうでしょうか?
慰謝料については、慰謝料を支払う側、慰謝料を請求する側の双方について、概ね次のような要素を考慮して算出されます。
【慰謝料を支払う側・請求する側に共通する要素】
・婚姻期間の長さ
・年齢
・子どもの有無
・親権の有無
・結婚生活で夫婦がどれくらい協力し合ったか
・社会的地位や支払能力の程度
【慰謝料を支払う側の要素】
・不倫やDVなど、明確に離婚原因となったといえる行為(有責行為)があるか
・上記有責行為の違法性の程度(頻度、継続期間など)
【慰謝料を請求する側の要素】
・離婚によって生じた精神的苦痛の程度
・慰謝料を請求する側にも離婚に至らしめた責任があるか、また、その責任の程度
・慰謝料を請求する側の離婚後の経済的自立の程度、可能性
上記の構成要素のうち、医師など高年収な職業の場合に影響する要素は「社会的地位や支払能力の程度」になります。
ただ、もちろん他にも慰謝料を算出する要素は多く、結局他の要素に相殺されて一般的な相場と変わらない場合もあります。
医師の場合、慰謝料は高額になりやすいとはいえ、その影響は限定的と考えて良いでしょう。
むしろ、財産分与、養育費、婚姻費の方が年収による影響は大きいと思われます。
不倫や浮気が原因で離婚する場合の証拠集め

離婚で慰謝料を請求するには「明らかな不法行為」であることが必要になりますから、不法行為であることを立証しなければいけません。
ここでは、慰謝料請求の理由の中でもかなり多い、不倫や浮気について、どのように立証するかを紹介します。
怒りに任せて問い詰めるのはおすすめしない

医師の不倫や浮気については、同じクリニックの看護師との浮気など、かなり身近なところで発生していることも多いです。
ですから、奥様が知っている人が浮気相手になっていた、というケースがあります。なかには、奥様が同じクリニックで働いていた場合もあります。
それだけに「怪しい!」と感じたら怒りが頂点に達し、パートナーを問い詰めたくなるでしょう。
しかし、それはパートナーに警戒する機会を与えてしまうことになるので、逆効果になる可能性が高いです。
不倫や浮気が発覚すれば、怒りが頂点に達する気持ちもわかるのですが、慰謝料を請求したいのであれば、黙っておいた方が良い場合もあります。
重要なことは、パートナーを問い詰める前に、こっそりと証拠を集めることです。
テレビ番組で、探偵の浮気調査の特集を見ていても、調査で証拠が確定するまで黙っていることが多いと思います。
いざ慰謝料を請求するときに、「いつの間に!」と思わせるくらい証拠を集めましょう。
不倫や浮気の証拠をどうやって集めるか?

不倫や浮気の証拠を集めるには、最初に思いつくのが探偵に依頼をすることです。
探偵に依頼し、2人がホテルに入る証拠をおさえてもらえば、決定的な証拠となります。
そのためには、探偵にパートナーの行動パターンをしっかりと伝えるようにするようにしましょう。
ただ「お願いします」と言っても、何もわからないと探偵も尾行が困難になってしまいます。
一方で探偵に依頼するのではなく、自分で証拠を集められるなら集めても良いでしょう。
ドラマでよく見るシーンですが、パートナーのスマホをチェックするのも重要な証拠集めです。
例えばLINEのやり取りは重要な証拠です。スクリーンショットなどでしっかり保存しておきましょう。
浮気調査に使えるアプリも活用

ただ、パートナーのスマホをチェックするといっても、ドラマのワンシーンのように盗み見することは難しいでしょう。
通常はロックがかけられているはずですし、指紋認証やFACE-IDなど、セキュリティはどんどん厳しくなっています。
しかし最近は「パートナーのスマホを見たい」というニーズに応える浮気防止アプリが数多くリリースされているので、活用すると良いでしょう。
このような浮気防止アプリでできることと言えば、次のようなことを苦労しなくてもできるようになります。
・SNSのメッセージログの閲覧
・保存された画像や動画の閲覧
・通話履歴の確認
・今どこにいるのかを確認
・どこを経由したのかを確認
・カメラ機能の強制起動など
例えばmSpyはLINEやSMSのやり取り確認、インターネットの閲覧記録調査、通話記録の確認が可能です。
【まとめ】慰謝料は不法行為があって初めて請求できる
以上、慰謝料はどんなときに請求できるのか?そのくらいの相場なのか?についてお伝えしました。
慰謝料は不倫やDVなど、相手の不法行為によって発生する賠償金です。
離婚に関するお金の問題は、まず慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費を区別して解決するようにしていきましょう。
なお、財産分与や養育費、婚姻費などについては、以下の記事も参考にしてください。
【関連記事】【開業医の妻の実態】意外と多い医師の離婚|慰謝料、財産分与、養育費は?
【関連記事】医師と妻が離婚で揉めないために知っておきたい財産分与の話


監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。