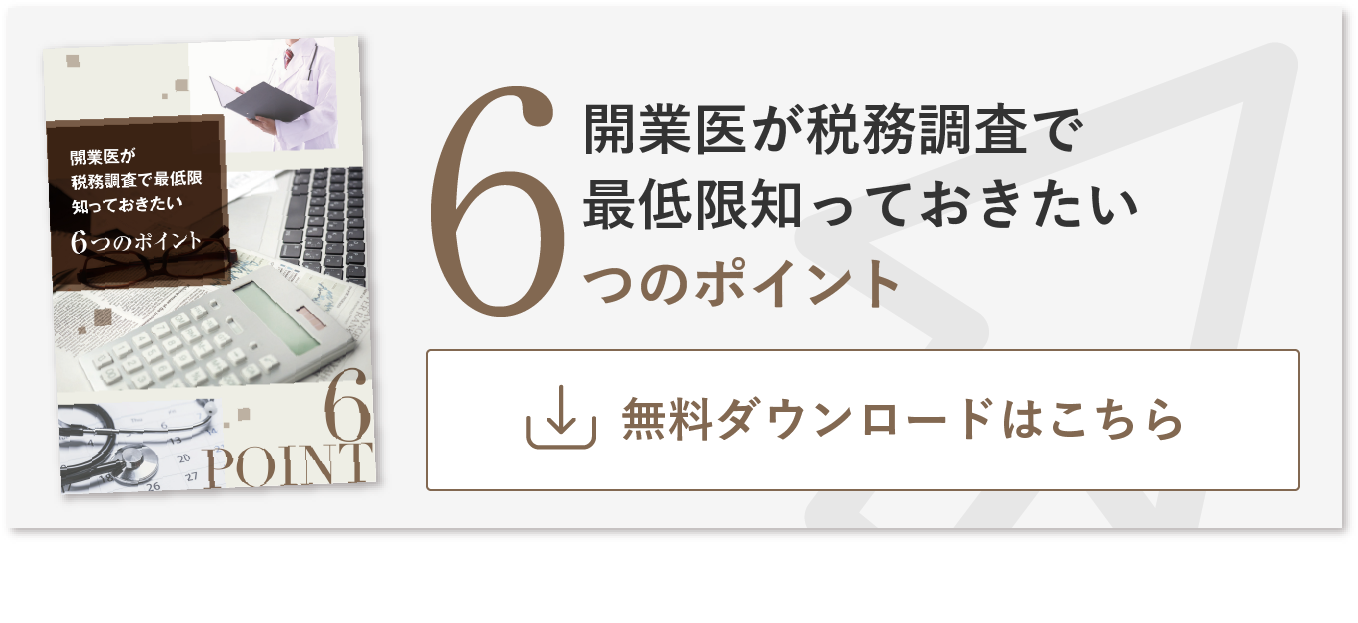【クリニックの賞与】看護師の退職後にボーナスを支払わないとだめ?


「去年の10月から3月まで働いた分のボーナス(賞与)は6月にもらえますよね?」
3月いっぱいでクリニックを自己都合退職するスタッフから、こんなことを言われました。
このクリニックは、10~3月までを賞与算定期間として6月に夏季のボーナスを支払っていました。
この場合、院長先生は退職する看護師の言う通り、退職後にボーナスを支払わないといけないのでしょうか?
就業規則でボーナスについてどう定めているのかが重要
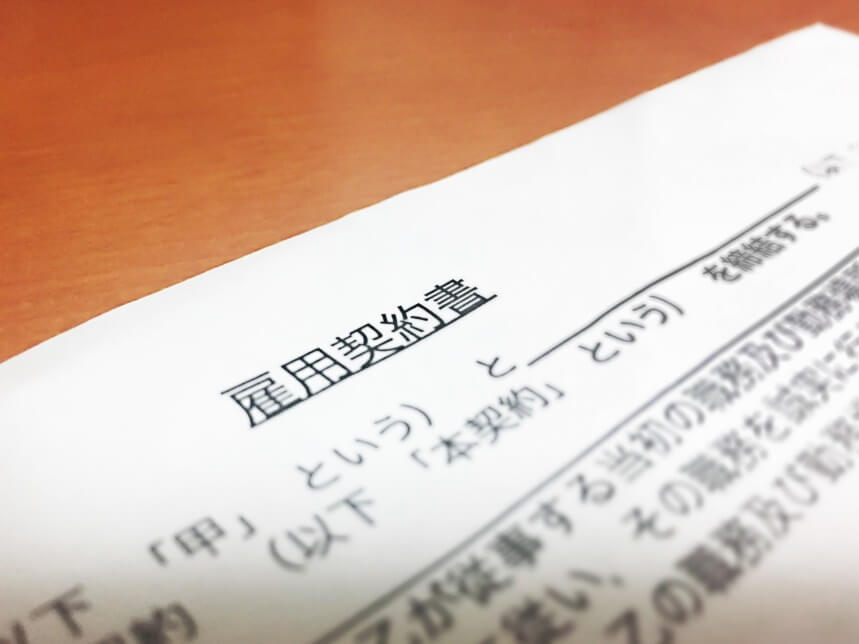
ボーナスは労働基準法で「絶対に払わないといけない」と定義されているわけではなく、クリニックの院長先生の裁量で決められます。
しかし、だからといって当然適当に支給しては、スタッフ間の格差を生むなどトラブルが起きやすくなります。
そのため、大半のケースでは就業規則などでボーナスの明確な基準を定めています。
(賞与)
第50条:賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
算定対象期間 支給日 月 日から 月 日まで 月 日 月 日から 月 日まで 月 日 2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
引用元:厚生労働省「モデル就業規則」より抜粋
つまり、ボーナスについては全般的に、就業規則でどのように定めているかが大きなポイントになります。
これは退職するスタッフ、すでに退職したスタッフに対しても同様です。(もちろん給与や退職金についても同じことが言えます)
自己都合退職する看護師にボーナスを支払わないようにする規定
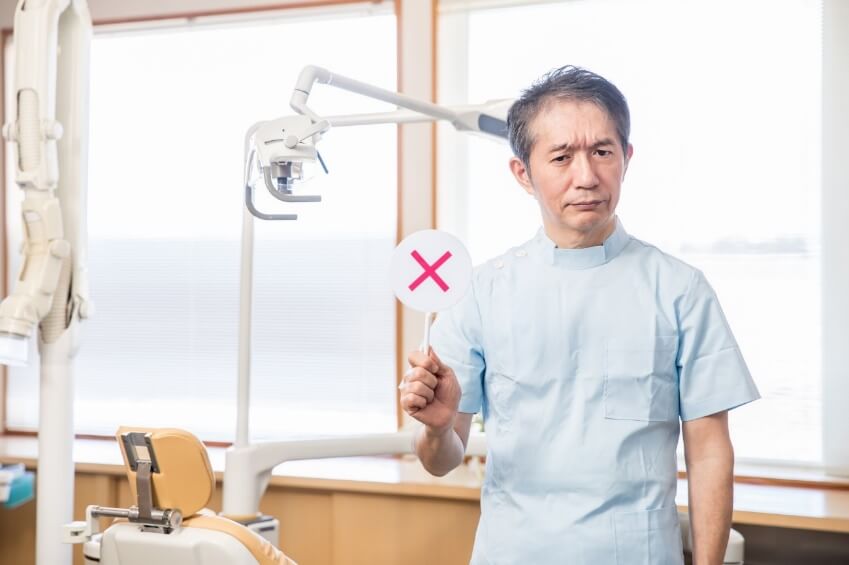
クリニック側の立場から見れば、基本的には給与もボーナスも在籍中のスタッフに支払いたいところです。
特にボーナスは、将来も引き続きスタッフとして働いてもらって、クリニックに貢献してもらいたいという意味合いがあります。
厚生労働省のモデル就業規則では、ボーナスに関して次のような解説があります。
2 就業規則に、賞与の支給対象者を一定の日(例えば、6月1日や12月1日、又は賞与支給日)に在籍した者とする規定を設けることで、期間の途中で退職等し、その日に在職しない者には支給しないこととすることも可能です。
引用元:厚生労働省「モデル就業規則」
つまり、看護師の退職後にボーナスの支払いをしないためには、就業規則や賃金規定で、次の支給日在籍要件の規定を設けることが必要です。
【支給日在籍要件の規定例1】
第◯条(賞与の支給日在籍要件)
前条の賞与の支給については、支給日に在籍している者に限り賞与を支給する。
【支給日在籍要件の規定例2】
第○条(賞与の支給日在籍要件)
前条の賞与の支給日に在籍しない労働者には、賞与を支給しない。
逆に就業規則等で支給日在籍要件の記載がないと、退職後のボーナスを支払わないようにするのは難しいでしょう。
冒頭の看護師は、もしかしたら就業規則を見て、上記の規定がないことを理由に退職後のボーナスを求めているかもしれません。
今はインターネットなどで労務に関することは簡単に調べられる時代です。
クリニックの労務対応に不満があれば、インターネットで何かしら調べていることは容易に想像付くので注意してください。
また、スタッフから冒頭のような要求があった後に、就業規則に支給日在籍要件を追加するようなことは避けましょう。
退職するスタッフに対して不利益変更をしたと判断される恐れがあるためです。
ボーナスに限った話ではないですが、このようなトラブルを避ける取り決めは新規開業時に確立しておくのが理想です。
10人未満のクリニックには義務付けられていない就業規則についても、早めに作成することがおすすめです。
なお、退職予定のスタッフは、退職日まで有休消化するケースが多いですが、有休消化取得中は在籍期間と判断されます。
最終出社日=退職日ではなく、有休消化中も支給日在籍要件を満たす点には注意してください。
会社都合退職や定年退職の場合はボーナスを支給しないといけないこともある

冒頭の看護師の退職のケースは自己都合退職ですが、会社都合退職や定年退職のように、スタッフ側で退職日を決められない場合について解説します。
自己都合退職以外の場合は、解雇など退職の原因がスタッフ側になるのか、クリニック側にあるのかで決められます。
後者の場合、支給日在籍要件を規定していても、退職後のボーナスの支払いを拒否することは難しいことがあります。
スタッフが自分の意思で退職するわけではないので、ボーナスの支払いを拒否することは不当と判断されることがあるためです。
例えば定年退職や人員整理を理由に解雇する整理解雇は、スタッフに非はありません。
このような場合は、基本的に「支給日在籍要件」は適用されず、満額ではないにしても、クリニックに在籍していた分の賞与は支払う必要があります。
一方、退職勧奨、諭旨解雇、懲戒解雇といったスタッフさんが原因で退職する場合の会社都合退職では、支給日在籍要件は、だいたい有効になります。
以上をまとめると、支給日在籍要件を定めた場合のボーナスの支払いは、次表のようになります。
| 退職の種類 | 退職後の賞与の支払い |
|---|---|
| 自己都合退職 | 不要 |
| 普通解雇 | 不要 |
| 整理解雇 | 必要 |
| 懲戒解雇 | 不要 |
| 諭旨解雇 | 不要 |
| 退職勧奨 | 不要 |
| 定年退職 | 必要 |
ただし、業績が著しく低下している場合は、上記のモデル就業規則のように記載しておけば、支給時期の延期、もしくは支給しないことも可能になります。
退職予定者の賞与の減額について
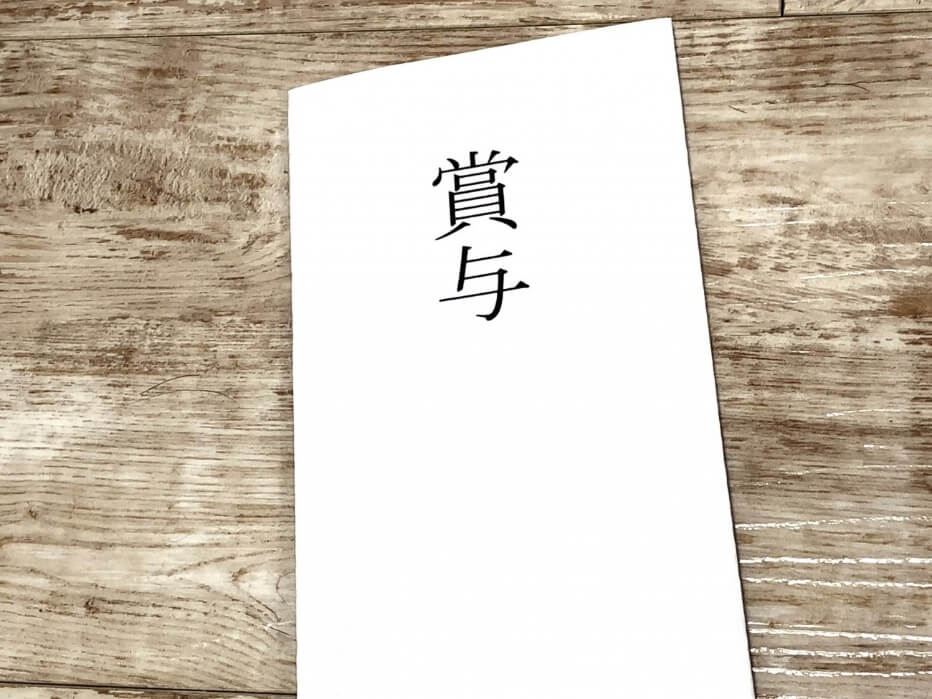
それでは、支給日在籍要件を定めると、ほとんどのスタッフはボーナスをもらってから辞めると考えられます。
冒頭の看護師も、院長先生から支給日在籍要件の話をすると、おそらく「それでは6月に辞めます」となるでしょう。
クリニックに限らず、一般企業でもボーナス月に退職する人はかなり多いです。
ただ、これからもクリニックに貢献するスタッフにボーナスを支払いたいと考えれば、納得いかないでしょう。
そのため、「せめて退職予定者のボーナスを減額できないか?」と考えるのではないでしょうか?
就業規則等に明記すれば賞与の減額は可能
退職予定者のボーナスを減額したいのであれば、やはり就業規則や賃金規程などにその旨を明記しましょう。
支給日在籍要件同様、明記していなければボーナスの減額はできません。
またボーナス月に辞めるスタッフが多いからといって、後で就業規則に追記すれば、やはり不利益変更になる可能性があります。
また退職予定者にはボーナスを減額する旨は、スタッフさんには必ず周知するようにしてください。
そうでなければ「聞いていない」と言うことになり、退職時にトラブルに発展する可能性があります。
ボーナスの減額は2割程度が目安
就業規則にボーナスの減額を規定するにしても、ではどのくらいカットすれば良いのでしょうか?
なかには8~9割カットしたいという先生もいるでしょうが、残念ながらそれは難しいでしょう。
ベネッセコーポレーション事件判決(東京地判平8.6.28)の例があります。
会社側では賞与支給後すぐに退職した社員に対して8割の賞与カットを求めました。
しかし、判決では賞与の減額こそ認めたものの、その減額はわずか2割でした。
実際の判例がありますから、退職予定であることを理由にボーナスを減額する場合は、最大でも2割程度の減額に留めるのが無難でしょう。
ボーナス減額の注意点
退職予定者のボーナス減額については、せいぜいできるとしても判例から2割程度と考えられますし、そもそも慎重にならないといけません。
退職予定者のボーナスを減額するなら、ボーナスの満額支給直後に退職届を提出することも考えられるためです。
民法627条では期間の定めのない雇用の解約の申入れについて、次のように定められています。
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
引用元:民法627条
月給制のクリニックで該当するのは、民法627条のうち1項と2項です。これを言い換えると、次のように言うことができます。
| 給与計算期間の前半までに退職の意思表示 | 当月末に退職が可能 |
| 給与計算期間の後半に退職の意思表示 | 翌月末に退職が可能 |
つまり、ボーナス支給まで退職の意思を隠しておき、満額支給直後に「院長、私辞めます!」と言って、当月末もしくは翌月末に退職することが可能です。
一方で、引き継ぎなどを考慮して、混乱がないように2~3ヶ月前に退職の意思を示すスタッフもいるでしょう。
早めに通知したスタッフのボーナスが減額され、急に退職届を出すスタッフのボーナスが減額されない。
と理不尽なことが起きる可能性があります。
しかも、スタッフの退職時期を縛ることはできないので、せいぜい就業規則には、「◯日前に上長の承認を得ることが望ましい」くらいにしか記載できません。
ボーナス月直後に退職したスタッフに、賞与の一部を返金する規定を加える方法もありますが、運用は慎重に検討する必要があるでしょう。
【まとめ】賞与に関する取り決めを明確にする
以上、クリニックのスタッフさんに対して退職後にボーナスを支払う必要はあるか? そして退職予定者のボーナスを減額できないか? という話をしました。
- 就業規則などで支給日在籍要件を明確に規定すれば、自己都合退職後のボーナスの支払いは不要
- 就業規則などで規定すれば、退職予定者のボーナスの減額は可能だが、支給減額と運用は慎重になる必要あり
このように、ボーナスに関する揉め事を避けるためには、就業規則などで明確に定めておかなくてはいけません。
後で追加するようなことになれば「不利益変更」と捉えられる恐れがあるので、できれば新規開業時に規定するのが理想です。
医院開業時に労働条件を取り決める際に、専門の社労士と相談してボーナスについても明確に定めていきましょう。


監修者
亀井 隆弘
社労士法人テラス代表 社会保険労務士
広島大学法学部卒業。大手旅行代理店で16年勤務した後、社労士事務所に勤務しながら2013年紛争解決手続代理業務が可能な特定社会保険労務士となる。
笠浪代表と出会い、医療業界の今後の将来性を感じて入社。2017年より参画。関連会社である社会保険労務士法人テラス東京所長を務める。
以後、医科歯科クリニックに特化してスタッフ採用、就業規則の作成、労使間の問題対応、雇用関係の助成金申請などに従事。直接クリニックに訪問し、多くの院長が悩む労務問題の解決に努め、スタッフの満足度の向上を図っている。
「スタッフとのトラブル解決にはなくてはならない存在」として、クライアントから絶大な信頼を得る。
今後は働き方改革も踏まえ、クリニックが理想の医療を実現するために、より働きやすい職場となる仕組みを作っていくことを使命としている。