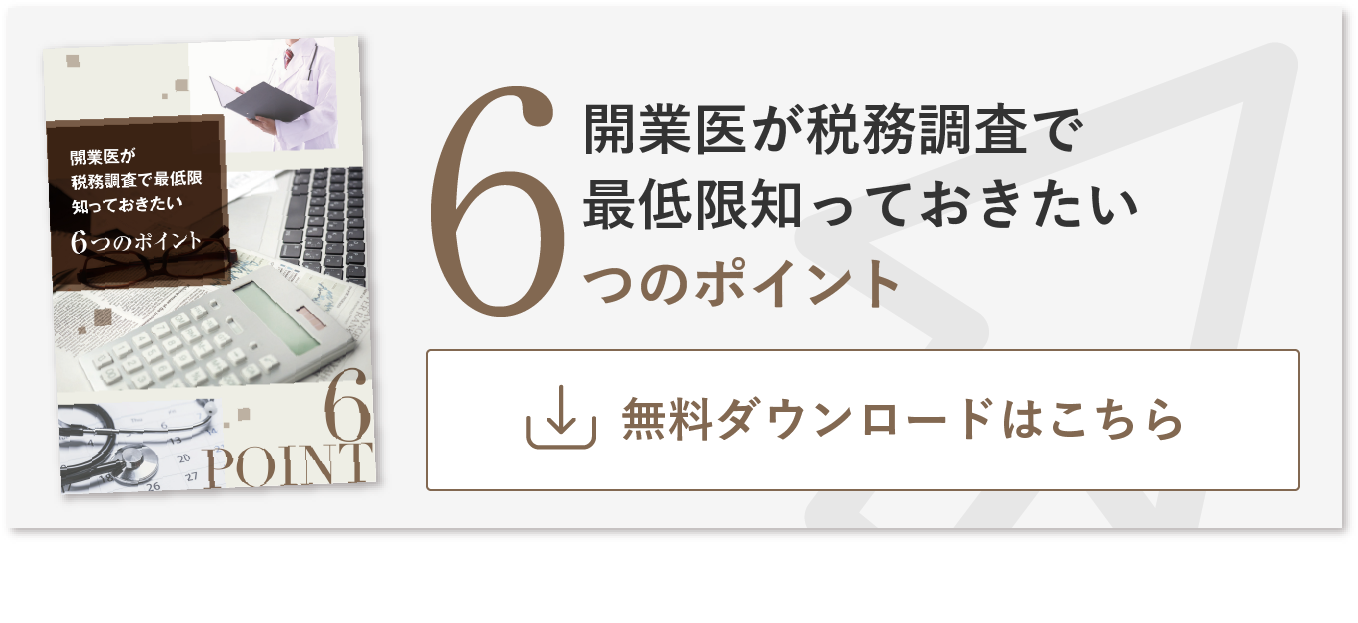クリニックの時短勤務|医師や看護師の短時間正社員制度の導入


2009(平成21)年の育児・介護休業法の改正で「育児のための短時間勤務制度」が登場し、全国の医院・クリニックで時短勤務が導入されていきました。
一方、似たような名称と内容になっている「短時間正社員制度」というものがあります。こちらも厚生労働省が推奨していますが、まだ全国的には普及しているとは言えません。
今回は、「育児のための短時間勤務制度」と「短時間正社員制度」の違いについてお伝えし、特に短時間正社員制度について詳しくお伝えします。
時短勤務などの柔軟な勤務形態の導入はクリニックの離職率の減少にも繋がっていきますので、院長先生はぜひご覧ください。
「育児のための短時間勤務制度」と「短時間正社員制度」の違い

まずは、似ているようで違う「育児のための短時間勤務制度」と「短時間正社員制度」の違いについてお伝えします。
簡単に概要を言うと、この2つの制度は以下のようなものです。
- 3歳未満の子供を養育する男女労働者について、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければいけない。(育児・介護休業法23条)
- 正職員の雇用形態のまま短時間で働く制度。育児・介護に限らず、特に利用期間も定められていない。
育児のための短時間勤務制度

こちらは冒頭にもお伝えしている通り、育児・介護休業法に則った制度で、具体的には育児・介護休業法23条1項で定められた制度です。以下条文を一部抜粋します。
事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。
引用元:第二十四条第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」
つまり、3歳未満の子供を育てているスタッフについては、申請があれば毎日の勤務時間を短縮する必要があるということです。
条件としては、3歳未満の子供を育てていること以外に、次の要件を満たす必要があります。
・本人から申し出があること
・1日の所定労働時間が6時間以上
・日雇い勤務でないこと
・育児休暇取得中でないこと
・就職後1年以上
・出勤日が週3日以上
つまり3歳未満の子供がいる場合は、本人からの申出があれば原則として所定労働時間を6時間まで短縮しなければいけないことになります。
短時間勤務制度については、就業規則の中でどのように運用していくか明示することが要求されています。
なお、原則所定労働時間は6時間とされていますが、本人の希望であれば7時間とすることも可能ですし、労働時間ではなく勤務日数を短縮することも可能です。
短時間正社員制度

一方で短時間正社員制度は、子供の有無に限らず、また育児の理由でなくても、正社員、正職員が所定労働時間を短縮できる制度です。
育児のための短時間勤務制度の影響を受けて設けられた制度のため、目的は似ているものがあります。例えば労働時間ではなく、勤務日数を短縮することが可能なところは一緒です。
大きく違うのは対象を問わないことです。育児のための短時間勤務制度は3歳未満の子供がいるスタッフだけが対象でした。
しかし、短時間正社員制度では、例えば「小学校入学前の一定の年齢まで」といった期間を設けることも可能です。
しかし、こちらは育児・介護休業法や労働基準法などの法律に規定されているものではないので、後述するようにあまり普及はしていません。
しかし短時間正社員制度をクリニックでも適用すれば、様々な勤務形態が可能になり、女性の多い職場では離職率の低下に繋がるでしょう。
時短勤務の場合の給与の支払いはどうする?

「育児のための短時間勤務制度」や「短時間正社員制度」といった時短勤務の場合、給料の支払いはどうなるのでしょうか?
結論から述べると、いずれの制度も基本的には時短分を無給にしても差し支えありません。
実際に「育児のための短時間勤務制度」も「短時間正社員制度」も、導入している事業所の多くは時短分を無給としているようです。
ただし、いずれの制度の場合でも、以下の点に注意しないといけません。
①時短分の給与が無給となり、賞与も減額となる件は就業規則に明記すること
②勤務時間に対する給与、賞与に対してスタッフの不利益とならないように設定すること(勤務時間の時給も減額するなど)
1つ目については、育児のための短時間勤務制度、短時間正社員制度ともに就業規則の記載例があるので、参考にしてください。
【育児のための短時間勤務制度】
4 本制度の適用を受ける間の給与については、 別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。
5 賞与については、 その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、 短縮した時間に対応する賞与は支給しない。
6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、 本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす引用元:厚生労働省「育児休業、短時間勤務制度 就業規則の作成のポイント」より抜粋
【短時間正社員制度】
第4章 賃金
第9条 短時間正社員の賃金については、正社員の所定労働時間に対する、短時間正社員の所定労働時間の割合に応じて、基本給、○○手当、○○手当を支給する。通勤手当は、所定労働日数が 1か月に○日以上の場合は、1 か月の通勤定期券代を支給し、1 か月に○日未満の場合は、1 日当たりの往復運賃に出勤日数を乗じた金額を支給する。第5章 賞与
第 10 条 賞与は、正社員の所定労働時間に対する、短時間正社員の所定労働時間の割合に応じて支給する。第6章 退職金
第 11 条 退職金算定の際の勤続年数の計算に当たっては、正社員として勤務した期間に、短時間正社員として勤務した期間を通算する。引用元:厚生労働省「短時間正社員制度 導入・運用支援マニュアル」より抜粋
短時間正社員制度の医院・クリニック側のメリット・デメリット

育児のための短時間勤務制度については、育児・介護休業法の定めによって、申請されれば認めなければならず、また制度の告知義務が発生します。
一方で短時間正社員制度については、育児のための短時間勤務制度に比べると法的な拘束力がありません。
法的な拘束力がなければ、気になるのが短時間正社員制度のメリット・デメリットとなるので、詳しく解説します。
短時間正社員制度のメリット
厚生労働省の「短時間正社員制度 導入・運用支援マニュアル」によれば、短時間正社員制度の雇用する側のメリットとして、次のものを挙げています。
・人材の確保
・人材の定着
・モチベーションの向上
・採用できる人材の幅の拡大
・働きやすい職場のアピール
・採用競争力の強化
・職場全体の働き方の見直し
・柔軟な働き方への対応(育児や介護、病気の療養、学び直し、副業・兼業等)
以下、簡単に解説しますが、いずれも個々の能力が発揮される職場環境である点と、人間関係が良好である点が前提になると考えられます。
そのため、短時間正社員制度を採用すれば職場環境が改善されるわけではなく、あくまで柔軟な働き方の選択の1つと考えるのがいいでしょう。
人材の確保・定着
育児や介護に限らず、病気や副業・兼業、通信教育などの事情で時短勤務を希望するスタッフを幅広く採用しやすくなります。
そのため、時間的な制限がありながらも労働意欲、能力ともに高い優秀な人材の確保や離職率の低減に繋がります。
柔軟な働き方によるモチベーションの向上
柔軟な働き方を認めることで、仕事やプライベート、学業、副業と両立させることができるので、働くことに不安要素がありません。
そのため、業務に集中することができてモチベーションの向上に繋がります。
採用できる人材の幅の拡大
時短勤務を採用することで、業務上様々な制約のあるスタッフを採用することができます。
そのため、スタッフの質と量を拡大できることに繋がります。
採用競争力の強化・働きやすい職場のアピール
短時間正社員制度は柔軟な働き方に対応できる制度なので、採用競争力の強化に繋がります。
求人募集しても、働きやすい職場であることをアピールできますし、時間の制約を気にしている求職者から応募が増えることも考えられます。
短時間正社員制度のデメリット
一方で、短時間正社員制度には、以下のデメリットが考えられます。
柔軟な働き方が可能になるとはいえ、場合によってはデメリットの方が大きくなることも考えられます。
責任ある立場を任せにくい
短時間正社員制度を適用した場合、責任ある立場を任せにくいというデメリットはどうしても出てきます。
管理職、マネージャー的な立場を持つスタッフに対しては、適用が少し難しいところがあります。
他のスタッフと不公平感が生まれやすい
給料に差があるとはいえ、時短勤務のスタッフと、通常のスタッフではスタッフ間に不公平感が生まれやすくなります。
そのため、通常の正社員が反発を覚えたり、時短勤務の正社員が早く帰りづらかったり(遅く出社しづらかったり)する可能性があります。
短時間正社員制度を導入するのであれば、育児のための短時間勤務制度同様に、他のスタッフにも制度について告知して、理解してもらうことが必要です。
また、時短勤務のスタッフが補助的な仕事だけにならないなど、通常のスタッフで仕事内容の差が生まれないようにする工夫が必要です。
必要な人件費用が増える可能性がある
あくまでも正社員なので、より自由に勤務時間を調整できるパート・アルバイトに比べると、必要経費が増える可能性があります。
そのため、後述するように、短時間正社員制度を適用できるスタッフの条件を設定するなど、事前検討が必要です。
社会保険と雇用保険の適用条件に注意する
時短勤務のスタッフの場合でも、正社員であれば社会保険や雇用保険は適用となります。
ただ、社会保険や雇用保険には適用条件があり、例えば週の所定労働時間20時間以上、社会保険であれば通常のスタッフの3/4以上勤務などです。
条件を満たしているかどうかは確認する必要があります。
短時間正社員制度の導入の検討事項が多い
短時間正社員制度がなかなか馴染まない背景として、法的な強制力がないことに加え、導入の検討事項が多いことがあります。
女性スタッフが多い医院・クリニックの場合、出産、育児・休暇以外に時短勤務や休暇のニーズがなければ導入する必要がないケースもあります。
対象の広い短時間正社員制度ですが、導入するのであれば、次のことを検討していく必要があります。
①短時間正社員制度導入の目的を明確化する
②短時間正社員に期待する仕事内容と仕事量を検討する
③短時間正社員制度の設計(適用事由、適用期間、労働時間)について検討する
④短時間正社員の処遇(賃金、人事評価、教育訓練)について検討する
⑤フルタイム正社員・短時間正社員間の転換、非正規雇用労働者から短時間正社員への転換について検討する
⑥短時間正社員制度を導入し、周知する
※厚生労働省「短時間正社員制度 導入・運用支援マニュアル」より抜粋
短時間正社員制度のメリット・デメリットを考慮し、自院に必要かどうかスタッフに希望を聞いてみるのもいいでしょう。
短時間正社員制度を導入するにはどうするか?

育児以外にも適用できる短時間正社員制度の導入を検討しているクリニックもかなり増えてきました。
長時間労働が蔓延しやすい医療業界では歓迎すべき取り組みですが、先に書いたように法的な規定がなく、あまり普及していません。
短時間正社員制度を導入するには、どのように戦略を立てていけば良いのでしょうか?
スタッフ間の不公平感を解消するように

短時間正社員制度によって多様な勤務形態が増えるほど、フルタイム勤務者や単身者の負担は大きくなります。
短時間正社員制度の導入は就業継続の切り札になる反面、スタッフ間に不公平感が生まれやすいのも事実です。
短時間正社員制度を導入する場合は、この不公平感を緩和するために、次の視点が欠かせません。
①ルール化する
②金銭的なインセンティブを与える(処遇で差をつける)
スキルを持った職員に限定する方法も

時短勤務は時短分の給料は差し引かれるのが一般的なため、子育て中のスタッフを除けば、さほど希望者は殺到していないようです。
「給料が差し引かれるくらいなら、フルタイムでがんばる」というスタッフが多いのも納得できます。
たしかにインターネットで検索しても時短勤務中の給料を気にしている看護師は多い印象です。
それでは短時間正社員制度の対象となるスタッフを絞り、そのスタッフだけフルタイムと同様の基本給を与える方法を取るのはどうでしょうか?
つまり、「クリニックのニーズに合った人材」「クリニックが求めるスキルを持った人材」に限定して短時間正社員制度を適用するのです。そして、減給はしません。
なぜかと言うと、優秀な人材が育児や介護を理由に離職することを防ぐためです。
これは机上の空論ではなく実際に医療機関の適用例があり、優秀な看護師が介護と仕事の両立を選択しています。
週休3日型の短時間正社員制度

先にも書いたように、短時間正社員制度は労働時間だけでなく、勤務日数を短縮する方法もあります。
実際に「週休3日型」の短時間正社員制度を導入している医療機関もあります。
なかには労働時間短縮型と勤務日数型両方選択できるクリニックがあり、短時間正社員制度により様々な勤務形態が可能になることを示しています。
例えば1日6時間×週5日勤務と、週休3日制といったような勤務形態です。
労働時間を短縮しても、「自分だけ早く帰りにくい」というスタッフがいるのも事実です。クリニック側としても「途中で帰られてはシフトを組みにくい」と考える院長先生もいるでしょう。
勤務日数が少なくとも、1日フルタイムで働いてくれた方がシフトを組みやすく、スタッフは帰りにくい状態を防ぐことができます。
つまり勤務日数短縮型の導入の方が、クリニック側としてもスタッフ側としても歓迎されることもあるのです。
実際に夜勤免除制度や短時間正社員制度を組み合わせた多様な勤務形態を導入している医療機関もあります。
この場合、ライフステージに合わせて勤務日数や労働時間を上げたり下げたりできます。
この場合は賞与査定を70~100%の間で調整したり、夜勤や休日出勤率が高いスタッフにインセンティブを与えるなど、公平感を保つようにしています。
このような柔軟な勤務形態を取り、それでスタッフ間の公平性を担保しているクリニックはまだ多くないのでしょう。
この医療機関では看護師などの応募者が増え、さらに離職率も大幅に低下したとのことです。
短時間正社員制度の助成金
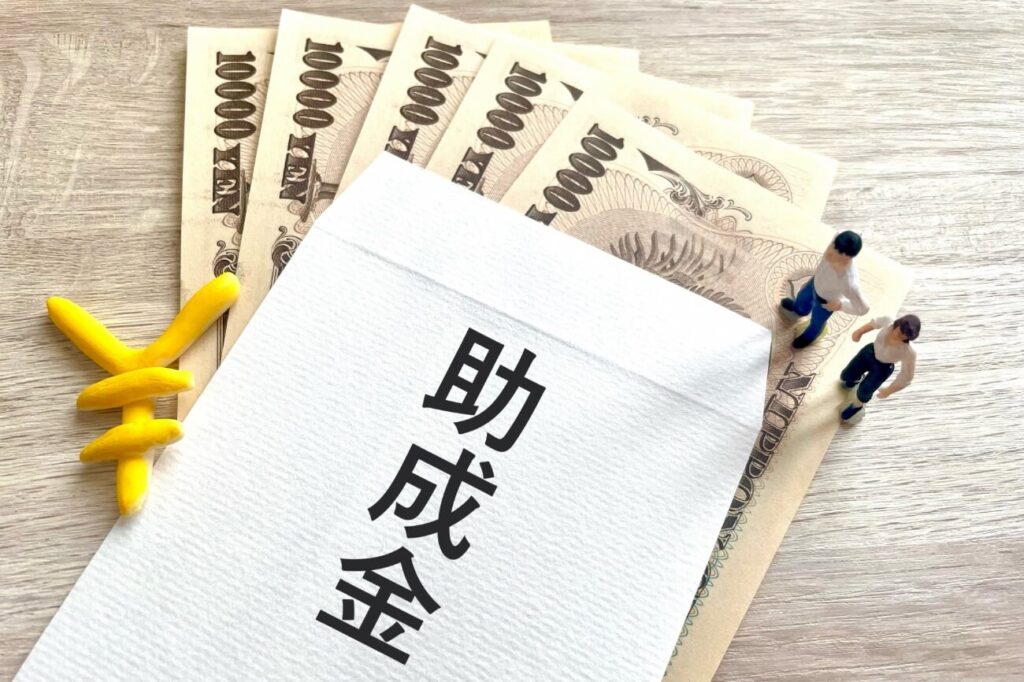
短時間正社員制度の導入によって得られる助成金には、キャリアアップ助成金があります。
キャリアアップ助成金には様々なコースがありますが、短時間正社員制度に該当するのは正社員化コースです。
正社員コースは、短時間正社員制度の導入により、育児や介護以外の理由でスタッフを雇用、もしくは短時間正社員に転換した場合に助成金が得られるコースがあります。
【キャリアアップ助成金 正社員化コースの概要】
※<>内は生産性の向上が認められる場合の額(1)支給額
①有期 → 正規:1人当たり 57万円<72万円>
②無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(2)加算措置
派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合
1人当たり28万5,000円<36万円>
● 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
(転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります)
①:1人当たり95,000円<12万円>
②:47,500円<60,000円>
● 人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合
①:1人当たり95,000円<12万円>
②:47,500円<60,000円>
● 「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合
1事業所当たり95,000円<12万円><1事業所当たり1回のみ>引用元:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内」をもとに作成
もし、短時間正社員制度を導入する際は、助成金の活用も合わせて検討するといいでしょう。
【まとめ】様々な勤務形態の導入で離職率の低下を

以上、「短時間正社員制度」を中心に時短勤務についてお伝えしました。
短時間正社員制度については、法的な強制力はないものの、導入することによって助成金活用、人材の確保、採用力強化などのメリットがあります。
柔軟な勤務形態を取ることで、優秀なスタッフが長く働いてくれることを期待できる一方で、導入時のデメリット・問題点があります。
短時間正社員制度を導入するかどうかは、最寄りの社会保険労務士に相談するようにしてください。
なお、短時間正社員制度を導入するかどうかに関わらず、現在は正職員のスタッフとパート・アルバイトの不合理な待遇差が禁止されているので注意してください。


監修者
亀井 隆弘
社労士法人テラス代表 社会保険労務士
広島大学法学部卒業。大手旅行代理店で16年勤務した後、社労士事務所に勤務しながら2013年紛争解決手続代理業務が可能な特定社会保険労務士となる。
笠浪代表と出会い、医療業界の今後の将来性を感じて入社。2017年より参画。関連会社である社会保険労務士法人テラス東京所長を務める。
以後、医科歯科クリニックに特化してスタッフ採用、就業規則の作成、労使間の問題対応、雇用関係の助成金申請などに従事。直接クリニックに訪問し、多くの院長が悩む労務問題の解決に努め、スタッフの満足度の向上を図っている。
「スタッフとのトラブル解決にはなくてはならない存在」として、クライアントから絶大な信頼を得る。
今後は働き方改革も踏まえ、クリニックが理想の医療を実現するために、より働きやすい職場となる仕組みを作っていくことを使命としている。