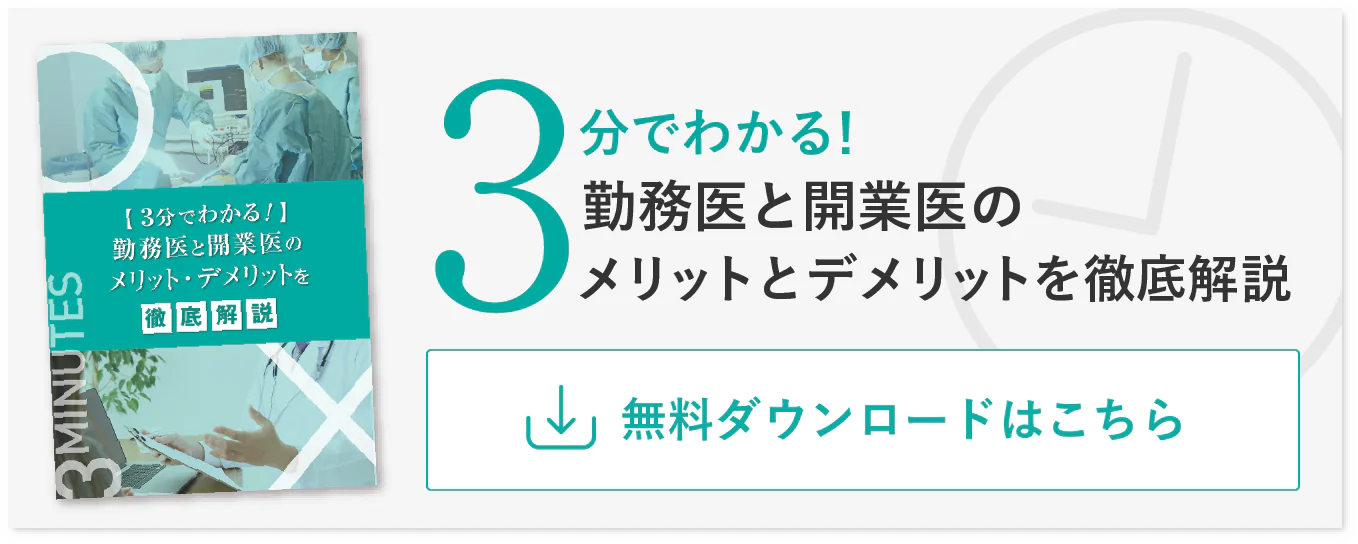小児科の開業医・勤務医の年収は? 開業の必要資金、物件選びや集患対策のポイントも詳しく解説


小児科で開業しようと考えている先生に向けて、開業医の年収や、勤務医との比較、開業資金の目安について解説します。
また、小児科クリニックは、主に小さいお子さんを持つお母さんが来院するため、他の診療科目とは違った視点で物件選びや集患対策が必要です。
そのため、開業資金の目安だけでなく、物件選び、集患対策という点でも詳しくお伝えします。
※開業医の年収や開業資金は個人差がかなり大きく、バラツキがあるので、あくまで参考までにご覧ください。
医療経済実態調査から見る小児科の開業医の年収と内訳

小児科の開業医の年収については、第22回医療経済実態調査のP350にある一般診療所(個人・青色申告を含む)で、医業・介護収益から費用を引いた損益差額を年収とすると、2827.3万円と算出できます。
同調査から算出される全開業医の平均年収は2,763万円(健保連の算出)なので、全診療科目の平均とほぼ同じ水準と言えます。
小児科の収支の内訳については、以下の通りです。
なお、この年収については、税金や社会保険料、借入金の返済額といった経費にならない支出は含まれていないので、実際の手取りはもっと少なくなります。
収益の内訳
第22回医療経済実態調査を元に小児科開業医の年間収益の内訳を示すと、医業収益は8,859.9万円となっています。
さらに収益の内訳を見てみると、入院診療の内訳の割合は0%となっており、大半の収益は外来診療(7,891.1万円、構成比88.7%)から構成されています。
入院診療の構成比が0%なのは、小児科の他に皮膚科のみです。
また、保険診療の割合は、外来診療の74.9%ほどを占めていますが、他科に比べれば保険診療の割合は少ない方です(多くの診療科目では90%を超えている)。
経費の内訳
小児科の開業医の年間経費(医業・介護費用)は6,032.7万円となっています。
また、小児科開業医の年間経費の内訳を以下の表にまとめると、次の通りとなり、他科と構成比に大きな違いがないことがわかります。
| 小児科開業医 | 開業医全体 | |
|---|---|---|
| 経費 | 6,032.7万円(68.4%) | 5,842.7万円(68.1%) |
| 給与費 | 2,237.7万円(25.0%) | 2,330.7万円(27.2%) |
| 医薬品費 | 1,995.4万円(22.4%) | 1,333.6万円(15.6%) |
| 材料費 | 97.8万円(1.0%) | 190.3万円(2.2%) |
| 給食用材料費 | 0.0万円(0.0%) | 16.9万円(0.2%) |
| 委託費 | 98.9万円(1.1%) | 271.1万円(3.2%) |
| 減価償却費 | 303.1万円(4.2%) | 369.4万円(4.3%) |
| その他 | 1,299.9万円(14.7%) | 1,330.8万円(15.5%) |
小児科の勤務医の年収

小児科の勤務医の年収は、独立行政法人 労働政策研究・研修機構「勤務医の就労実態と意識に関する調査」(2012年)によれば1,220.5万円です。
開業医と勤務医の平均年収は2倍以上の開きがあると言われますが、小児科医の場合も同じような特徴で、約2.3倍もの開きがあります。
勤務医の場合は年齢によって年収は大きく違いますが、勤務医の場合は年収が1,500万円くらいで頭打ちする傾向にあります。
それに比べれば、小児科の開業医は2倍以上の年収が見込めることになります。
しかし、開業医の場合は年収が青天井の分、逆に収益を上げられずに廃業・自己破産のリスクもあります。
このリスクは小児科の場合も同様で、開業する場合は、開業コンセプトを明確にして物件を選び、必要資金を算出しないと、開業後に苦労することになります。
小児科の開業資金は基本的には他科と大きく変わらない

小児科の開業資金は、他の診療科目とあまり大きな違いはなく、考え方も大きな変更はありません。
開業コンセプトによって大きく違いはあるでしょうが、戸建て物件での開業の場合は、土地、建物だけで3,000万円以上かかると見込んだ方がいいでしょう。
テナント開業でも内装費用などを見込めば1,000万円以上はかかります。
各種医療機器の購入を考えれば、最低でも4,000~5,000万円の開業資金に、初年度の運転資金を用意しておくのがいいでしょう。
この規模感は、内科とあまり変わらないかと考えられます。
なお、小児科で開業される先生は、内科を兼ねて開業されるケースも多いので、内科開業医の年収や開業資金についての記事も併せてご覧ください。
【関連記事】内科の開業医の年収は?勤務医の年収との比較と開業資金についても解説
小児科の開業物件の特徴と開業資金

なお、内科と小児科の大きな違いは、言うまでもなく患者さんの属性です。小児科は小さいお子さんの患者さんと、付き添いの親御さん(特にお母さん)が来院することになります。
そのため、一般的には駅前のビルやオフィス街よりは、郊外の住宅街の方が相性はよくなります。
拙著「開業医の教科書®」では、「都市部と郊外」「駅前と住宅街」「昼間人口と常駐人口」の立地の特徴やメリット・デメリットについてお伝えしています。
このなかで小児科の立地は、どちらかというと「郊外」「住宅街」「常駐人口」に該当するかと考えられます。
ただ、この条件をすべて満たした立地では、競合が多い傾向にあります。
また、必ずしも郊外の住宅街でなければ集患できないわけではなく、誰も気づかないような好立地条件もあるので、詳しいことは専門家にご相談ください。
また、小児科の開業物件は、小さいお子さんとお母さんが来院することを考えると、次のことを考慮に入れた方がいいケースもあります。
- テナント開業なら1階もしくは2階以上なら広いエレベーター付で、ベビーカーを押している親御さんでも簡単に来院できること
- 郊外の住宅街の場合は、駐車場のスペースを確保しておくこと
- 感染症対策で隔離室の設置スペースがあること
このように、他科と違った視点で開業物件を検討する必要があります。
開業資金については、基本的には上記のようなイメージですが、高額な駅前のテナント物件でなくてもいいので、もう少し抑えられるかもしれません。
しかし、場合によっては建物や土地に広さを求められることも考えられるので、その場合は開業資金が割高になります。
小児科を開業するなら少子高齢化の影響も考慮する

どの診療科目でも、診療圏調査などで競合となる小児科を調査したり、開業後の見込み来院患者数の目安を算出したりします。
小児科の開業で気を付けないといけないのは、少子高齢化の影響です。
内科・小児科で開業するのであればさほど大きな影響はありませんが、開業地域の少子化の影響を考えて物件を選ぶ必要があります。
地域によって少子高齢化が進むエリアと、逆に保育園など子育て環境が良くて子どもの人口が増えるエリアがあります。
小児科の集患対策や患者満足度の向上

小児科の集患対策や患者満足度の向上については、小さいお子さんと親御さんが来院するという点で、他科と少し違う注意点があります。
良くも悪くも口コミの影響を受ける
小児科は、他科に比べて、大きく口コミの影響を受けやすい診療科目です。
小児科の主なターゲット層となる小さいお子さんのいるお母さんは、良くも悪くも口コミの影響力が大きいためです。
「スタッフの対応が親切で安心感がある」
「予約システムがしっかりしていて待ち時間が短い」
「感染対策を徹底していて安心感がある」
「先生の感じがよくて、しかもすぐに治る」
このようないい評判があればお母さんの間でいい口コミが広まり、勝手に集患しやすい仕組みができあがります。
逆に「スタッフや先生の感じが悪い」「治らない」「待たされるし周りの子どもがうるさい」という悪い評判もあっという間に広がり、患者さんが遠のいてしまいます。
グーグルマップやポータルサイトの口コミの投稿を促す戦略は重要ですが、日頃から患者満足度の向上を意識しないと逆効果になるので注意しましょう。
キッズルームの設置は慎重に
小児科の場合は物件を決める際に注意したいのは、キッズルームの設置です。
以前は、待ち時間の長いお子さんのためにキッズルームを設けることが多かったです。
しかし、一方で子ども同士が騒ぐことや、感染対策の観点でかえって悪評に繋がることがあり、現在では設置しないケースが増えています。
キッズルームは待ち時間が長い場合の対応策の1つですが、近年はWebの予約システムの導入などで待ち時間の短縮を図る工夫が進んでいます。
そのため、近年のキッズルームを設置するよりも、予約システムで待ち時間を短縮する仕組みを確立する方が合理的と思われます。
キッズルームを作るのであれば、それだけ開業資金が余計かかりますし、デメリットが大きいなら無理に設置する必要はないでしょう。
しかし、子どもが喜ぶようなモノがまったくいらないというわけではなく、待合室で絵本やおもちゃを用意するなどの工夫は必要です。
感染症対策の徹底
新型コロナウイルスの影響で、他の感染症への警戒心も強まっています。
もともと小児科は、水痘、おたふくかぜ、風疹などの子どもの感染症患者も多いです。
そのため、隔離室を設けたり、感染症が疑われる患者さんとそうでない患者さんで動線を分けたりするなど、院内感染の防止対策を徹底することが必要です。
実際に院内感染が起きなくても、院内感染の防止策があるかないかで親御さんの安心感に大きく影響します。
感染対策に不満があるだけで悪い口コミが広がることもあり得るでしょう。
そのため、開業資金を検討する際は、隔離室の設置など十分な感染対策も考慮するようにしましょう。
【まとめ】小児科開業は小さいお子さんを持つお母さんを意識した集患対策を
以上、小児科の開業医の年収や、開業物件の考え方、集患対策についてお伝えしました。
小児科の先生は内科と兼ねて開業するケースも多いですが、基本的には年収や開業資金の規模感は、内科と大きく変わりません。
大きく変わるところというと、開業準備や集患対策の考え方でしょう。
小児科は、他科とは違う患者さんの属性があるため、小児科独自の開業準備や集患対策が必要なことがあります。
日々の診療はもちろんのこと、待ち時間の減少や感染対策、スタッフ教育の徹底などで患者満足度の向上を図るようにしましょう。
口コミの影響が大きいので、日頃からいかにお母さんが安心してお子さんを連れてこられるかが、集患や医業収入を左右することになります。


監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。