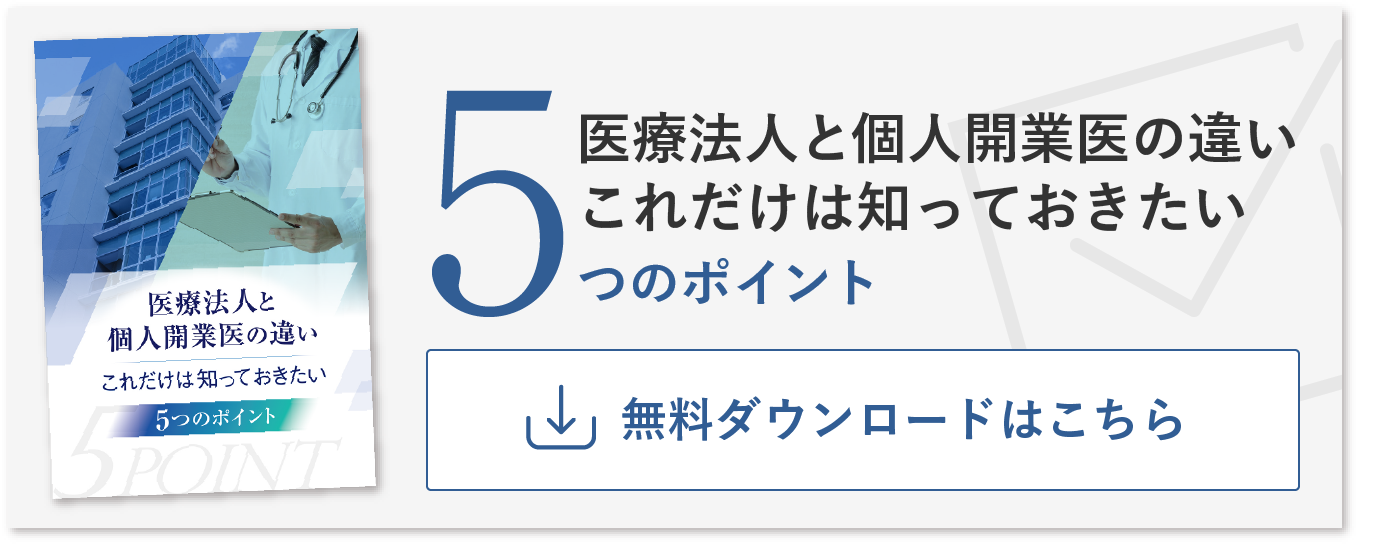【開業医の遺産相続】遺言書の活用、こんなときどうする?
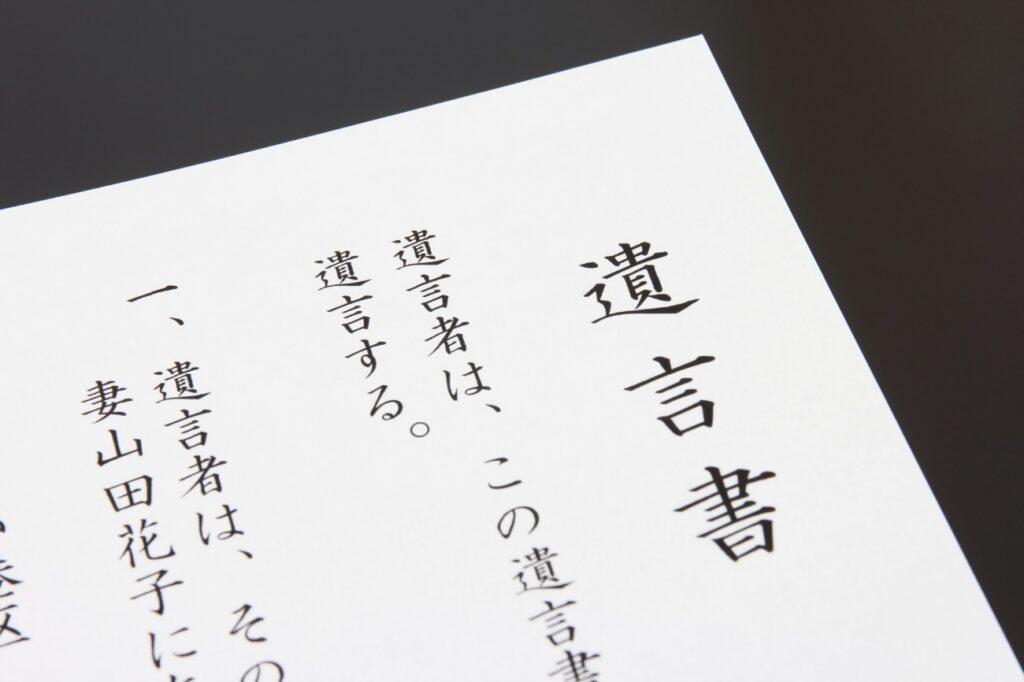
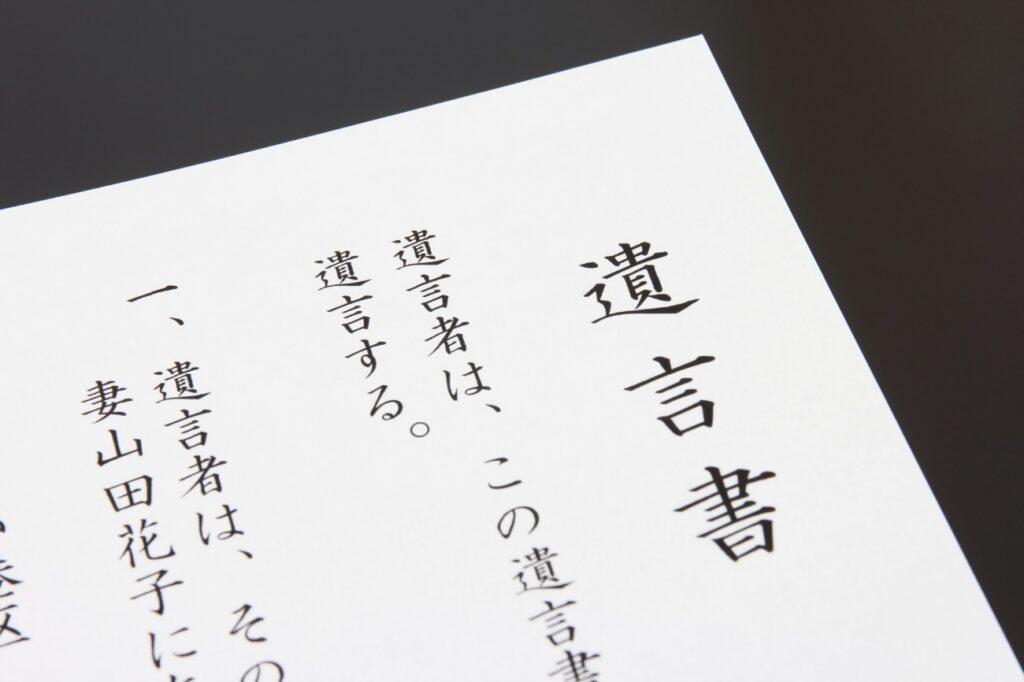
国内で相続税の対象になる人は全国民の5%と言われているものの、開業医の先生の場合は比較的財産が多く、相続税がかかる可能性が高くなります。
普通預金や不動産、株式に加え、医療法人の場合は出資持分(旧法の医療法人の場合)、医療法人への貸付金(理事長借入金)も相続税の対象です。
また、近年遺産分割に係る司法争いは増加の一途をたどっています。令和元年(2019年)に家庭裁判所で争われた遺産分割調停事件は約12,875件でした。
このような相続対策や揉め事が起こる場合に備え、事前に「遺言書」を作成することをおすすめします。
しかし遺言書は法律に沿って作成されなければ効果がありません。自己流で遺言書を作成しても意味はなく、意図する通りに財産を残せないこともあります。
そこで今回は、遺言書の制度と活用事例について、詳しくお伝えしたいと思います。
自筆証書遺言と公正証書遺言について

遺言書は代表的に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
秘密証書遺言は、どうしても内容を相続人等に秘密したい場合に選択されますが、実態としては、ほとんど使用されていません。
どうしても内容を秘密にしたい場合以外は、「自筆証書遺言」もしくは「公正証書遺言」どちらかを選択することが一般的です。
自筆証書遺言

自筆証書遺言は、被相続人が遺言を自筆で書き遺す方法です。作成ルール、メリット、デメリットについて詳しくお伝えします。
自筆証書遺言の作成方法
紙やペンの指定はありませんが、以下の民法第968条に従ったルールに従って書く必要があります。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
引用元:民法第968条
つまり、次のことを満たさなければ、自筆証書遺言の内容はすべて無効となるので、作成には注意が必要です。
- ・自筆で書くこと
- ・日付を自筆で正確に書くこと
- ・記入者の氏名を自筆で記入すること(戸籍謄本に記載の本名が一般的)
- ・印鑑を押すこと(実印が安心)
- ・財産目録はパソコン等の入力でも可能だが、すべてのページに印鑑が必要
- ・財産の記載については、できるだけ詳細に記載すること
- ・相続人には「相続する」、相続人以外は「遺贈する」と表現すること
自筆証書遺言のメリット
- 1人で手軽に作成できる
- コストを抑えることができる
- 自筆証書遺言保管制度を利用すれば、紛失のリスクを抑えられる
- 自筆証書遺言保管制度を利用すれば、検認不要
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言は1人で手軽にいつでも作成できるのがメリットですが、一方で次のようなデメリットがあるので注意が必要です。
- 形式や内容の不備で無効になる恐れがある
- 偽造、変造される可能性がある
- 被相続人がこっそり作成することがあるため、遺言書を紛失や、存在を知られない可能性がある
- 一部の相続人に不利な内容の遺言書の場合、破棄されたり隠匿、改ざんされたりする可能性がある
- 検認が必要(自筆証書遺言保管制度を利用すれば不要)
- 遺産分割協議後に遺言書が見つかる恐れがある
自筆証書遺言は検認手続が必要
自筆証書遺言の発見者や保管者は、家庭裁判所に対して遺言の検認手続の申立てをしなければなりません。
家庭裁判所は、遺言書の要旨、筆記用具、内容、日付、署名、捺印の情報を記録します。
遺言書に封がされている場合には、開封せずに検認を申し立てなければなりません。
もし開封してしまった場合には、偽造、変造の意図がなく開封したとしても5万円以下の過料(行政罰)が科されるので注意が必要です。
また1度開封されてしまうと、「遺言が偽造もしくは変造された」と疑われることになるので、相続人の方は注意が必要です。
ただし、次に話すように、自筆証書遺言保管制度を用いれば、検認手続きは不要になります。
自筆証書遺言保管制度
自筆証書遺言保管制度とは、紛失、隠匿、改ざんなどのリスクを防ぐため、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法) によって、2020年7月より施行された制度です。
遺言書保管法の制定により、被相続人が自分で保管の申請手続きをすることで、自筆証書遺言を法務局に保管できるようになりました。
これにより、自筆証書遺言のデメリットである紛失や隠匿、改ざんリスクを防ぐことができ、検認も必要ありません。
しかし、自筆証書遺言保管制度は、法務局が遺言書の内容が適正かチェックするものではないため、遺言書が無効になるリスクはそのまま残ります。
公正証書遺言
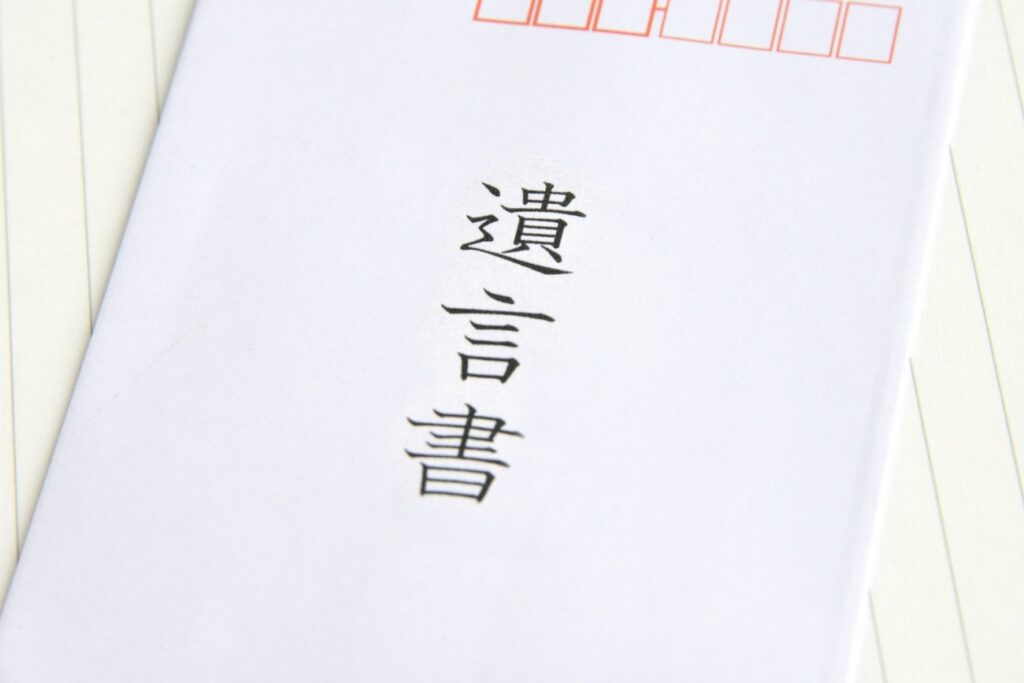
公正証書遺言は、遺言者が公証人の目の前で遺言の内容を打合せ、証人2人の立会いのもと、その内容に基づいて遺言者の真意を正確に文章にまとめて作成する方法です。
ここで、公正証書遺言で言うところの公証人、証人とは、次のような人のことを言います。
| 公証人 | 法務大臣から任命され、指定された公証役場に配置された者 |
|---|---|
| 証人次に該当しない者(民法第974条)で、公証役場の紹介を受けることも可能 ・未成年者 ・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 ・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 |
公正証書遺言について、作成ルール、メリット、デメリットについて詳しくお伝えします。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は、次の民法969条に則ったルールに従って作成する必要があります。
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。引用元:民法969条
具体的には、次の流れで作成することになります。
- ①自筆証書遺言と同様に遺言の内容を考え、決まったら必要書類を集める
- ②必要書類(※)を持って、公証役場に電話して事前にアポイントをとり、公証役場で公証人と内容などの打合せをする
- ③公証人から書面作成完了の連絡が入り、作成期日を決める
- ④作成期日に証人2人と公証役場へ行き、遺言に署名押印する
- ⑤公証役場に手数料を支払って、遺言公正証書の正本と謄本を受け取って完了
※必要書類……印鑑登録証明書、戸籍謄本、相続人以外の遺贈が発生する場合はその人の住民票、不動産がある場合は登記事項証明書と固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書。
公正証書遺言のメリット
- 形式や内容の不備による無効のリスクがない
- 偽造や変造のリスクがない
- 隠匿や改ざんのリスクがない
- 紛失しても再発行が可能
- 紛失しても再発行が可能
今は自筆証書遺言でも、紛失や改ざんのリスクは少なくなっていますが、公正証書遺言は、無効になるリスクがないのが何と言っても大きくなります。
公正証書遺言のデメリット
- 手間や費用がかかる
- 公証人と証人2名が必要
遺産額に応じた作成費用がかかり、公証人の面前で証人2名の立会いのもと作成しなければなりません。
形式的要件を満たせば自分だけで作成ができる自筆証書遺言と比べると、手間もコストもかかるので不便ではありますが、確実な方法です。
自筆証書遺言と公正証書遺言どちらがおすすめ?
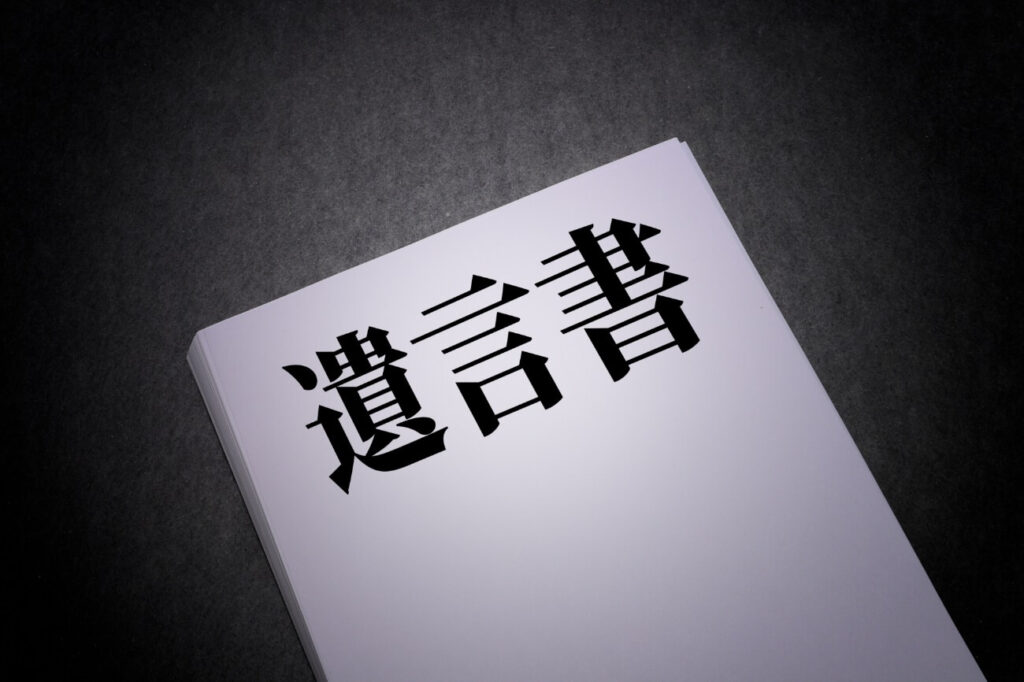
もし、相続が発生するので遺言を遺そうとお考えの場合は、無効や紛失のリスクのない公正証書遺言の方をおすすめします。
自筆証書遺言は、少しでも不備があると無効になってしまう恐れがどうしても残ってしまいます。
また、自筆証書遺言の場合、被相続人の死後、遺産分割終了後に遺言書が見つかることもあります。
後述するように、その場合は、遺言の効力のほうが上回るため、相続人全員の同意がないと遺産分割をやり直すことになってしまいます。
【遺産相続・遺言書Q&A】こんなときはどうする?

ここまで代表的な遺言書についてお伝えしましたが、もちろん個々の状況によって対応は変わってきます。
そこで、ここでは代表的な遺産相続や遺言書の事例と、具体的にどのようにしていけば良いかをお伝えします。
遺産がクリニック関連の不動産のみの場合

資産の大半をクリニック関連の不動産が占めている場合は要注意です。
相続人が複数いる場合、不動産は分割できないため不公平となり、相続争いが起こる可能性があります。
その場合、クリニックを売却せざるを得ない事態になる可能性があり、クリニックを引き継いだ遺族は職場を失うことになりかねません。
このような場合に備えて、例えば遺言で次のように指定しておくと良いでしょう。
- 「不動産を相続するのは長男の◯◯とする」などとする
- 次男などには相当額を代償金として支払う旨を記し、その代償金分として、後継者を受取人とする生命保険契約を準備しておく
遺産分割で揉めるのが明らかな場合

生前から相続人が不仲で、死後もめることが明らかな場合は遺言書を用意しておくことをおすすめします。
「長男には診療所の◯◯を、次男には◯◯市の土地を、三男には△△株式会社の株式1,000株をそれぞれ相続させる。残りの現金などの遺産は3人に均等に分割する」
遺言書は、相続の場では大きな効力を持ちますので、上記記載例のように「具体的に」遺言書に記載すれば揉める可能性は少なくなります。
この「具体的に」というところが重要で、遺産をもれなく記載して相続人を記載する必要があります。
ひとつでも相続する遺産が抜けていたり、曖昧な状態だと、そこが火種となって対立することがあるので注意してください。
子供がいない場合

結論から言うと、遺言書の用意は不可欠です。
例えば子供のいない夫婦で、夫が死亡したとしましょう。
通常、子供がいる場合には、妻が2分の1、子供が2分の1の相続分で相続することになります。そのため、子供がいなければ、妻がすべて相続すると思い込んでいる方が多いです。
しかし、基本的には妻がすべて相続することにはなりません。各々のケースにあてはめてみましょう。
子供がいなくて、亡くなった夫の親が生きている場合
まず、亡くなった夫の親が生きていれば、妻に加えて、夫の親も相続人となります。この場合、法定相続分は妻が3分の2、親が3分の1となります。
ただ、夫が夭折した場合を除き、現実的にはこのケースはあまり多くないと思われます。特に開業医の先生の多くは、このケースはあてはまらないでしょう。
子供がいなくて、亡くなった夫の両親も死亡している場合
夫の親がすでに死亡していれば、今度は夫の兄弟姉妹が相続人となります。 この場合、法定相続分は妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
このケースで問題なのは、夫の兄弟姉妹と日常的にコミュニケーションを取り合っている例はあまり多くないと推測されることです。
疎遠な関係にある夫の兄弟姉妹と遺産分割協議を円滑に進めることが困難に陥ることは珍しくありません。
しかも現在のお年寄り世代はまだ兄弟姉妹が多いので、この疎遠な関係はかなり厄介と言えます。
子供がいなくて、亡くなった夫の両親、さらに兄弟姉妹の誰かも死亡している場合
さらに厄介な例が、夫の兄弟姉妹のなかで、すでに死亡している人がいる場合です。もちろんこのケースも珍しくないのですが、その場合は甥や姪も相続人となります。
甥や姪とは面識があって、仲良くしている例はかなり少ないと言えます。そもそも現在甥や姪が何をしているのか把握していない人や連絡先がわからない人も多いでしょう。
遺言書を作成して、具体的な相続人と遺産を示すと揉めにくい
このように、子供がいない場合は配偶者にとっては疎遠な関係にある親戚と遺産分割協議をすることになってしまいます。
このような場合に、遺言の効力を活用するのです。
夫が遺言書を作成し、「妻に遺産のすべてを相続させる」など具体的な相続人と遺産を示すと良いでしょう。
二次相続まで指定したい場合
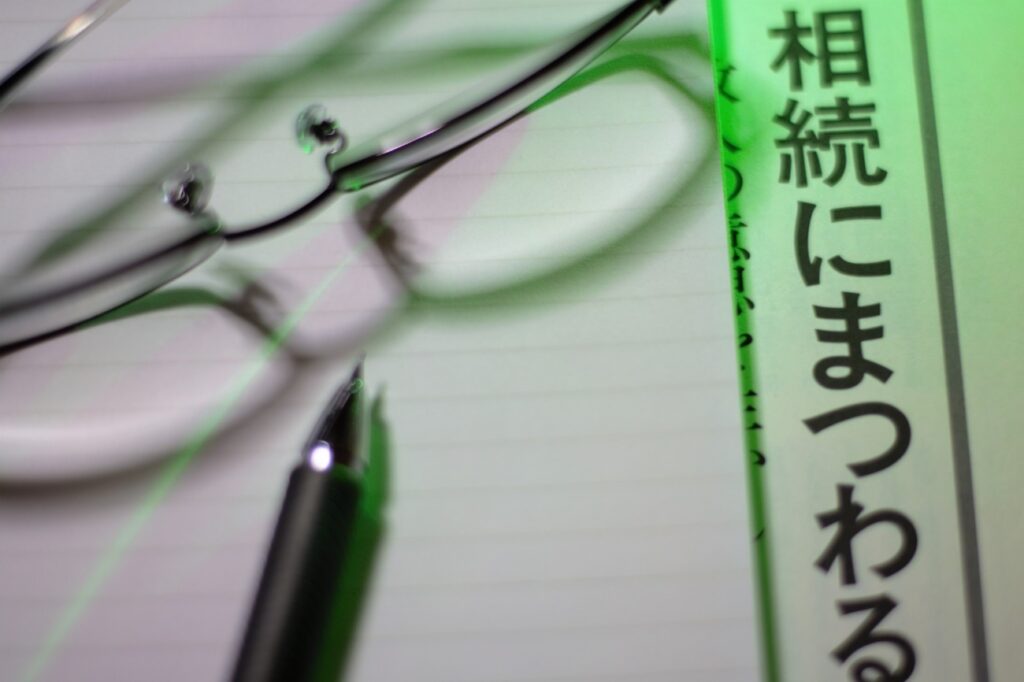
次の二次相続まで指定したい事例を考えてみます。
(1)Aさん(非相続人)と妻Bさんの間には子供はいない。
(2)Aさんの財産は投資用不動産であり、家賃収入で生計を立てている。
(3)Aさんが亡くなった後は妻のBさんに財産を渡したいが、Bさんが亡くなった後は、Aさんの兄弟のCさんに財産を譲りたい。
遺言では二次相続まで指定できない
相続財産は死後すべて妻Bさんに残したい。この点は遺言を活用すれば解決です。
しかし、次にBさんが死亡すれば投資用不動産が妻の法定相続人となる妻の親族側に渡ってしまいます。
最終的に兄弟Cさんに財産を承継させるためには、Bさんにその旨の遺言書を書いてもらう必要があります。
しかし、それは妻Bさんの気持ち次第で、BさんがCさん以外の人に相続する意思があれば、Cさんが相続できない可能性があります。
このように二次相続まで自分で指定できないのは、遺言の限界の1つと言えます。
二次相続まで指定するなら信託のスキームを活用する
このAさんの事例のように二次相続まで指定したいのであれば、信託のスキームを使用すると良いでしょう。
信託とは、自分の財産を信頼できる人に預け(所有権の移転)、その人に財産の管理・処分をしてもらう制度です。
信託のポイントは、受益者(信託財産から得られる利益を受け取る人)を信託契約のなかで自由に決めることができる点です。
Aさんの場合は「受益者連続型信託」という仕組みを活用すると良いでしょう。
受益者連続型信託とは、あらかじめ受益者の順位を指定しておき、現受益者が死亡した場合、受益権が順次承継される仕組みです。
このように指定しておけば、二次相続、三次相続のことまで心配がなくなります。
信託活用時の税法上のデメリット
ただし、受益者連続型信託には税法上のデメリットもあるので注意が必要です。
受益権の評価は信託時の時価で引き継がれ、しかも死亡により受益権が移転する都度信託財産に対して課税されます。
つまり、短期間に次々と相続が発生して受益者が代わっていくような信託契約は、多大な税金が発生する可能性があります。
例えばAさん所有の投資用不動産の評価額が1億円、年間の家賃収入が500万円とします。
この場合、AさんとBさんの死後、Cさんはすでに高齢で、あと5年くらいしか生きられない状況で受益者になったとしましょう。
その場合、500万円×5年=2,500万円の受給権しか得られないことになります。それなのに、評価額1億円に対する相続税を課されてしまうことになるのです。
二次相続、三次相続を考える際は、このように受益者の寿命も考慮しないと、逆に負担をかけてしまうことになるので注意が必要です。
法定相続人以外に財産を遺したい場合

遺言書がない場合、民法で定める法定相続人ではない他人に個人の遺産を遺贈させることはできません。
ですから他人に財産を遺したい場合は、遺言書を作成する必要があります。
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
引用元:民法第964条
例えば「内縁の妻Yに現金5,000万円を遺贈する」などと記載すれば、本来相続人にならない内縁の妻に遺産を遺すことができます。
この場合、「相続する」と記載するのではなく必ず「遺贈する」と記載しましょう。
ただし、法定相続人以外に財産を遺す場合は、次のようなことに注意する必要があります。
法定相続人以外に財産を遺す場合は相続税額で不利になる
法定相続人以外に財産を遺す場合は、次のように相続税額において不利になるので注意しましょう。
・非相続人の一親等の血族、および配偶者以外の人の場合、相続税額の2割加算が適用
・法定相続人以外の場合は、未成年者控除、障害者控除などの税額控除が適用されない
法定相続人は遺留分減殺請求が可能
遺留分とは法定相続人の権利のことを言いますが、法定相続人は遺留分減殺請求が可能になります。
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害されている法定相続人が、受遺者に対して侵害額を請求することです。
このようなトラブルを避けるためには、事前に遺留分を考慮することが大切です。
法定相続人以外の受遺者に遺贈する場合は、法定相続人にも遺留分相当の資産を分配することでトラブルを回避しやすくなります。
自分で遺言書を書ける状態にない場合

一般的に、遺言書を作成する人は高齢者の方が多いです。
つまり、体が不自由な場合、万が一の場合、認知症の疑いがあるような場合も珍しくありません。
このような場合に、効力のある遺言書を遺すにはどうすれば良いのでしょうか?
体が不自由な場合
体が不自由な場合は、自筆証書遺言を書くのは難しいでしょうが、公証人の代筆によって公正証書遺言を作成するのが一般的です。
遺言書を作成する段階では、病気や体力の衰えなどで公証役場まで移動が困難な場合もあるでしょう。その場合は公証人に自宅あるいは病院まで出向いてもらうことも可能です。
口頭で公証人に遺言内容を伝えますが、口が不自由、耳が聞こえなくなっている場合もあるでしょう。
こうした場合、筆談や通訳人の通訳を通じて公証人に意思を伝え、公正証書遺言を作成することが可能です。
万が一の状況が迫っている場合
遺言書は決められた様式を守らないといけないため、実際に書面にするには手間がかかります。
ただ、いつ万一の事態がやってくるかはわかりません。開業医の先生とはいえ、正確な自分の死期を悟るのは難しいでしょう。
そもそも、交通事故や脳疾患、心臓疾患のような急病で、万が一の状況が迫ることも多いです。
このような状況にも遺言を遺せるように、法的効力をもつ遺言として「危急時遺言」というのが定められています。
危急時遺言は、証人3人以上が立ち会い、その1人に遺言の趣旨を口頭あるいは通訳人の通訳により伝えます。
そして証人が筆記し、それを遺言者と他の証人に確認をとり、署名捺印することで作成します。
この遺言書については、遺言があった日から20日以内に家庭裁判所の確認を得なければなりません。
なお、遺言者が通常の方式によって遺言するようになった場合、その後6ヶ月生存したら、危急時遺言の効力は失われます。
この場合でも、再度遺言を遺すのは忘れないようにしましょう。
認知症の疑いがある場合
遺言者は満15歳以上で、遺言書を作成する際に意思能力を有していれば、誰でも遺言をすることができます(民放961条)。
これを逆に言えば、認知症で意思能力がなければ遺言書は無効ということになります。
ただ、意思能力については「物忘れが増えた」「理解に苦しむ行動が目につくようになった」という「グレーゾーン」に該当する場合もあります。
このような場合は、必ずしも遺言が無効となるわけではありません。
判断が困難な場合は医師の診断書を取得し、医学的に意思能力に問題がない証明書として保管することをおすすめします。
その方が、後日トラブルになる確率は低くなります。
ただし、医師の診断書があるからといって、必ず遺言書が法的に有効となるわけではありませんので注意しましょう。
「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」の遺言作成
認知症の話をすると、それでは、「被補助人」「被保佐人」「成年被後見人」に関してはどうか気になる方もいるでしょう。
各々の判断能力レベルについては、次のように定義されています。意思能力レベルとしては、「成年被後見人」>「被保佐人」>「被補助人」となるでしょう。こちらは下の図を見てわかるように、各々認知症の場合も含まれます。
| 類型 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
|---|---|---|---|
| 意思能力レベル | 常に意思能力を欠いている人 | 意思能力が著しく不十分な人 | 意思能力が不十分な人 |
| 例 | 脳死認定をされた方、重度の認知症を患っている人 | 日常の買い物程度ならできるが、大きな財産を購入したり、契約を締結したりすることは難しい人、中度の認知症の人 | 日常の買い物はひとりでも問題なくできるが、援助者の支えがあったほうが良いと思われる人、軽度の認知症の人 |
遺言書を作成する際は、「被補助人」や「被保佐人」の場合は、特に制限は設けられていません。
一方、自己の財産管理ができない「成年被後見人」は意思能力を欠いていると判断されるため、基本的には遺言書を作成することはできません。
ただし「全然話を理解していないと思っていたら、突然理路整然と話し始めた」というように、一時的に意思能力が回復することがあります。
一時的に意思能力が回復した場合は医師2人以上の立会いの下、遺言書を作成することができます。
遺産分割後に自筆証書遺言が見つかった場合はどうする?
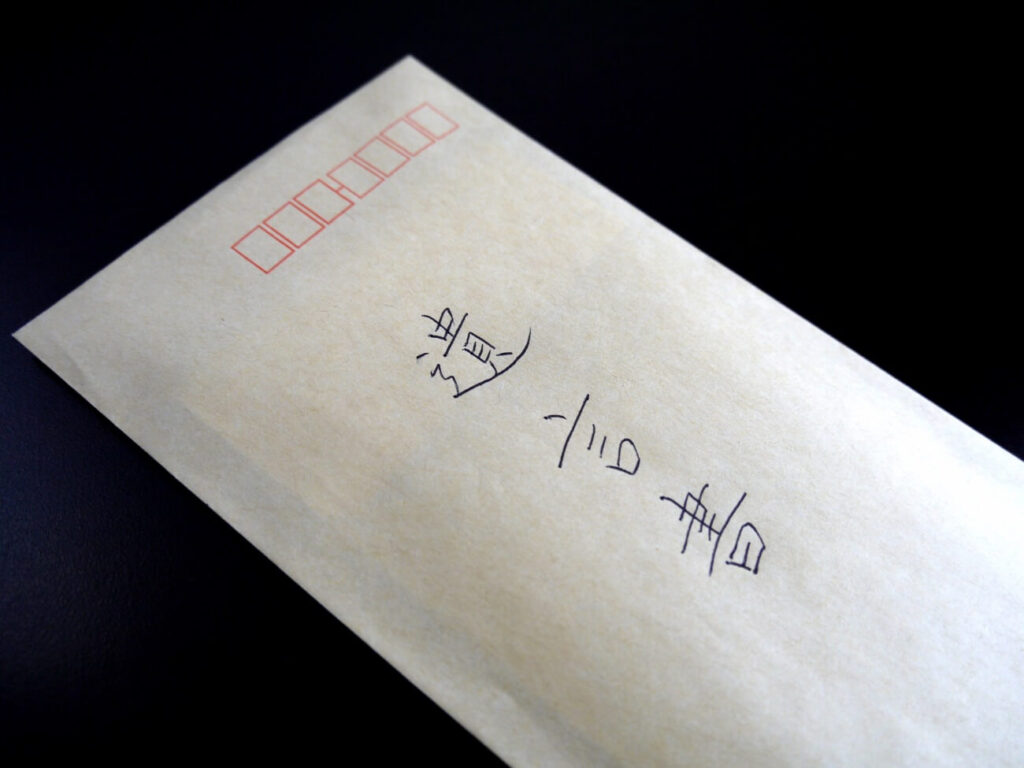
先ほどもお伝えしたように、公正証書遺言は、無効になるリスクがなくなるため、できれば、公正証書遺言を作成することが望ましいです。
しかし、家族に見られたくないという理由で、被相続人がこっそりと自筆証書遺言を作成し、亡くなるまで誰にも言わないケースが少なくありません。
この場合、被相続人が亡くなり、遺産分割協議が終わったあとに遺言書が発見されることがあります。
そうなると、遺産分割をやり直さないといけない可能性がありますが、次の6つのケースについて考えてみます。
遺産分割内容に相続人全員の同意があった場合
もし、発見された遺言書が有効とされた場合は、原則として「相続人全員の意思>遺言書>遺産分割協議内容」の順番で優先されます。
遺言書には時効がないため、数年後に発見された場合でも同様です。
「相続人全員の意思>遺言書」ですから、相続人全員で、「今まで通りで良い」と合意ができれば再協議の必要はありません。
遺産分割内容に相続人が1人でも異を唱えた場合
しかし、誰か1人でも遺産分割協議通りの相続に異を唱えたときは話が違ってきます。
優先順位は「遺言書>遺産分割協議内容」ですから、遺言書の内容をもとに、遺産分割をやり直さなければいけなくなります。
遺産分割協議内容と、遺言書の内容に大きな乖離があった場合などは、誰かが異を唱えることは十分考えられます。
「法定相続人以外に遺贈する」という遺言書の場合
先ほどもお伝えしたように、遺言書がない場合、民法で定める法定相続人ではない人に遺贈させることはできません。しかし、遺言書の存在が発覚すれば話が違います。
「遺言書>遺産分割協議内容」ですから遺言書の内容が優先され、遺産分割協議内容は無効となり、遺贈する必要があります。
もちろん、遺贈の権利のある本人が「遺産分割協議の内容通りで良い」と言った場合は、相続人全員が合意したことになるため、再協議の必要はありません。
「嫡出でない子どもの認知」を行う遺言書の場合
嫡出でない子を親子関係とするには、父または母が認知する必要があります(民法第779条)が、これを遺言書で行うことも可能です。
嫡出でない子どもを遺言書で認知した場合、認知によって相続人となった人から請求されれば、遺産分割をやり直すことになります。
「相続人の排除」の意思がある遺言書の場合
被相続人が、遺言で相続人の相続資格を排除する旨の意思を遺言書で示した場合は、相続人は相続の廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
引用元:民法第892条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
引用元:民法第893条
請求が認められれば、排除の対象とされた相続人の相続資格は剥奪され、遺産分割の内容が変動します。
「排除の取り消し」の意思のある遺言書の場合
逆に、生前被相続人が相続人の廃除を家庭裁判所に請求して認められたものの、遺言書で取り消しの意思を示す場合があります。
1.被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2.前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。引用元:民法第894条
この場合も、相続人が排除の取り消しを家庭裁判所に請求し、認められれば相続資格が復活するので、遺産分割の内容が変動します。
【まとめ】遺産相続の準備はお早めに
以上、遺言書の主な種類をお伝えし、事例別に遺産相続と遺言書の活用についてお伝えしました。
遺産分割については、相続税額のことも考慮し、慎重に相続人について考慮する必要があります。
遺言による相続が一番、相続人間の争いが起きずに確実です。しかし、無効のリスクの高い自筆証書遺言より、公正証書遺言にて遺言を作成することをおすすめします。
遺言書の作成を含め、生前の相続対策は専門家のアドバイスを聞きながら行うようにしてください。
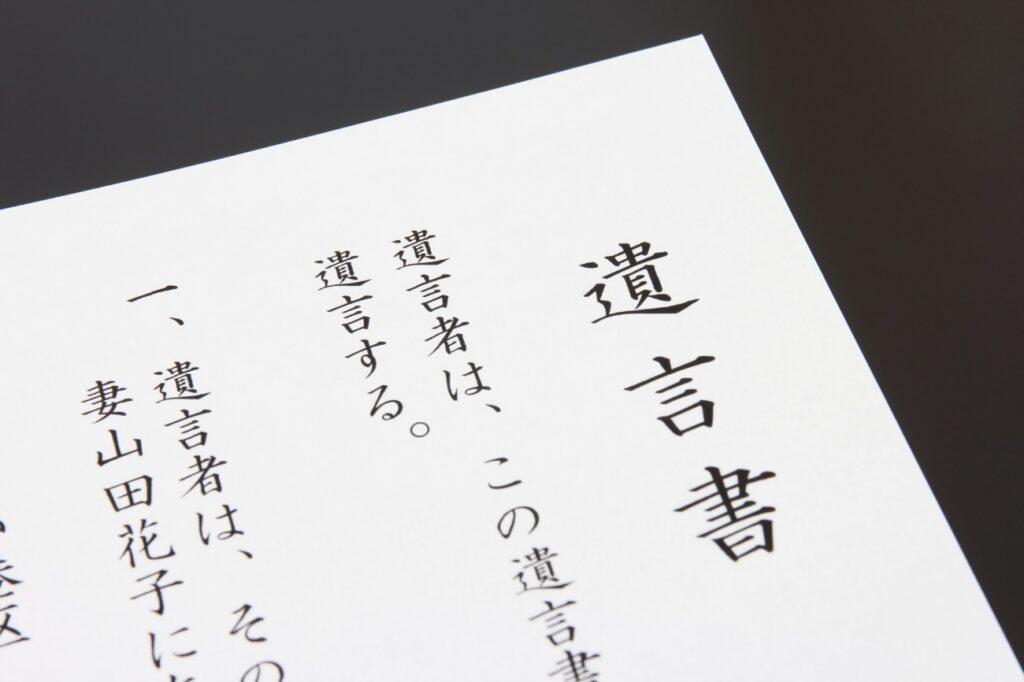

監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。