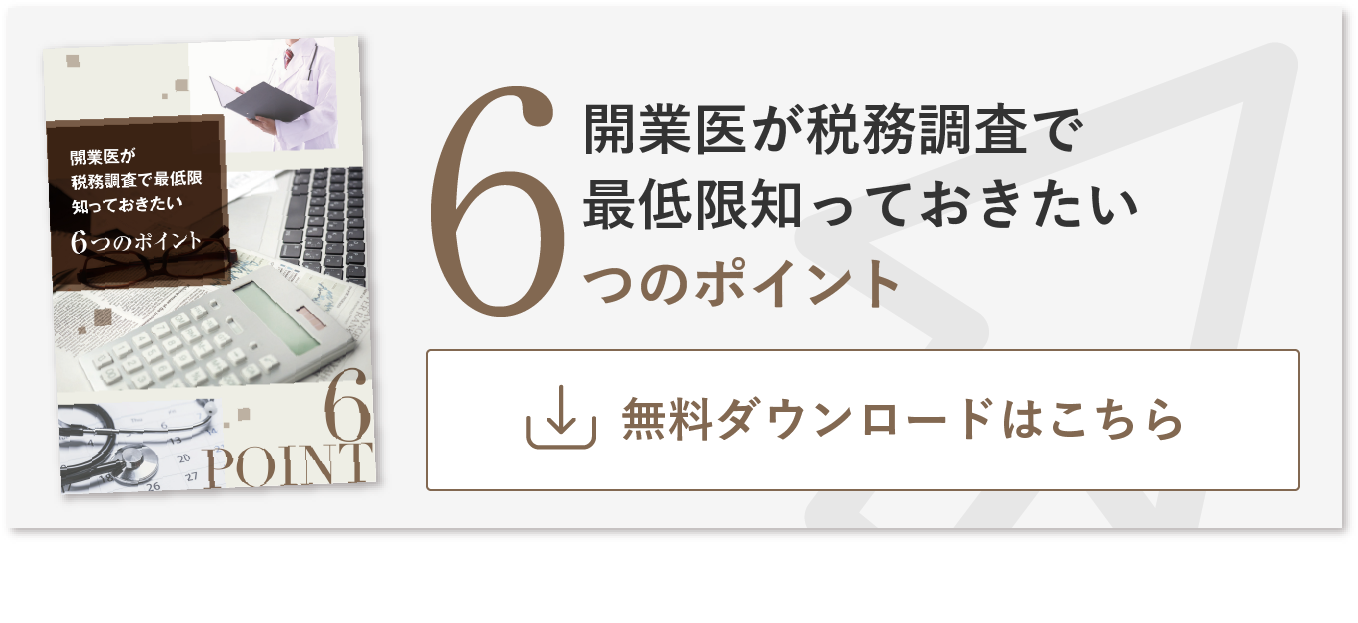なぜか患者が来ない!開業医の集患・増患対策6つの注意点


「クリニック開業前はもっと患者さんが来ることを想定していたのだが、実際に開業したら全然来ないな。もっと患者さんが来るはずだったのに」
医院・クリニック開業1~2年の時期、このように患者さんが思うように来ないとおっしゃられる開業医の先生は少なくありません。
実際開業直後はどうしても認知に時間がかかるので集患は難しいところはあります。
ただ、開業前に事業計画で想定していた数より少ないのであれば、何らかの対策が必要です。
立地が良ければ集患がうまくいくとは限りません。
立地条件の良い場所で開業しても、「思うように患者さんが来ない」と悩んでいる開業医の先生は比較的多いです。
しかも、立地条件がいい場所は開業資金もかかる傾向があるので、集患がうまくいかずに資金がショートして、1年足らずで廃業に至るケースもあります。
そこで今回は、特に開業直後の先生にとって重要な集患・増患対策のポイントについてお伝えします。
医院の集患とラーメン店の集客は全然違う

まず前提として、医院・クリニックの集患・増患対策とラーメン店の集客は全然違う特徴があります。
近所に新しいラーメン店ができた場合は、「なんか近くに新しいラーメン店ができたみたいだ。美味しそうだし行ってみようかな」となります。
そして、そのラーメンが美味しければ、「近所に美味しいラーメン店ができた」と口コミで広がっていくでしょう。
しかし、近所に新しい医院・クリニックができた場合はどうなるでしょう。
まず、「なんか近くに新しい内科ができたみたいだ。腕が良さそうだし行ってみようかな」とはならないでしょう。
また、別の例で言えば、行列のできるラーメン屋さんは「そんなに並んでいるなら食べてみよう」と自分も並びたくなります。
これをバンドワゴン効果と言いますが、医院・クリニックでは、これは当てはまらないでしょう(診療科目にもよります)。
「受付してから何時間も待たされるクリニックは腕が良い医者がいる証拠だ。今度行ってみたい!」とはなりません。むしろ評判を落とすことになるでしょう。
ラーメンは、毎日の食事で関わりのあるもので、日常的に興味・関心を持たれるものです。
しかし、医院・クリニックについては病気や怪我でもしない限り、興味を持つことはありません。
特に何か病気を持っているわけではなくて、健康な体で毎日過ごしている人にとって、日常的に関心がないものです。
関心がないので、どんなに立地の良い目立つところに開業しても、人々の記憶には残りません。
では、どういうときに「近くにできたクリニックに行こう!」と思うでしょうか?
当たり前ですが、病気や怪我をしたときです。
これを踏まえて、以下集患・増患のポイントをお伝えします。
どうやって患者さんは医院・クリニックを探すのか?

病気や怪我、例えば風邪を引いて「内科を探したい」と思ったとき、患者さんはどのように医療機関を探すでしょうか?
ほとんどの人は、まずスマホで近くの病院やクリニックを検索するでしょう。
例えば新宿の近くに住んでいる人や働いている人が風邪を引けば、「新宿 内科」と検索します。
今では地域名を入れずに、ただ「内科」と検索すれば近所の病院・クリニックが自動的に上位表示されます。
どんなに立地の良い場所で開業したとしても、スマホで検索してたどり着けなければ、患者さんが来ない可能性があります。
地域密着型の病院・クリニックであれば、立地条件やチラシやハガキが重要かもしれませんが、それでもスマホやネット検索が不要ということではありません。
病気や怪我といった急な事態ではネット検索する可能性が高く、今では高齢者もスマホで検索します。
もちろん、ホームページの制作費や広告費はかかりますが、最低限の対策は必要です。
なお、近所の患者さんに見つけてもらうか、遠くの患者さんにも来てもらうかによって対策は変わってきます。
例えば美容外科や美容皮膚科は、多少遠くても集患が見込めることがあるので、地域に限定しない対策も必要でしょう。
ただし、地域によってはネットでの集患の重要性は変わってくるので、地域に合った対策でないと必要以上に広告費がかかることになります。
もはや病院はSEO対策だけでは不十分?

「では少しお金をかけて、ホームページを作ってSEO対策をばっちりやっておこう!」
たしかにSEO対策は病院の集患・増患対策では大切なことです。
SEO対策を意識してホームページを作ることで、ある程度の効果は得られるでしょう。
しかし、SEO対策だけでは十分な対策とは言えません。
お手元のスマホで、実際に病院・クリニックを「内科」などで検索してみてください。

上の画像のように、最初に出てくるのはグーグルマップではないでしょうか?
順番的には、PPC広告の次にグーグルマップ、そして通常のオーガニック検索となっているでしょう。
そして、上位表示されたグーグルマップは非常に目立ちますよね。
実際に、グーグルマップ専用枠で上位表示された場合のクリック率は、PPC広告の7.5倍、通常検索の9倍と言われています。
※博報堂Dyグループ・スマートデバイス・ビジネスセンターのデータによる
このように、グーグルマップ専用枠に上位表示されるような対策をMEO対策と言います。
SEOがSearch Engine Optimizationの略であることに対し、MEOはMap Engine Optimizationの略です。
医院の集患に限らず、飲食店や整体院、エステサロンなど実店舗の集客では、MEO対策も必要です。
PPC広告よりお金をかけなくて済むので、費用対効果は抜群です。
しかし、MEO対策をすることで、グーグルマップで悪口を書かれ、悪い口コミが流れる可能性はあります。
また、ビジネス名に不要な情報(〇〇が得意! 〇〇No.1など)を入れたり、口コミを偽装したりするとペナルティを受ける可能性があります。
そのため、MEO対策でできることは少なく、自助努力でやることがほとんどです。
とはいえ、インターネットで認知を広げるためにはMEOの施策は行った方がいいでしょう。
なお、MEO対策を含め、ホームページの対策については、以下の記事にも詳しく書いています。
【関連記事】医院・クリニック開業時のホームページ制作で気をつけたい9つの対策
開業医のマーケティング戦略は立地条件によって違ってくる

先に書いたように、立地条件の良いところに開業したからといって、思うように患者が来るとは限りません。
開業した場所に併せたマーケティング戦略も必要になってきます。場所によって、ターゲットも変わってくるからです。
例えば、銀座や丸の内など、都心のオフィス街に医院を開業した場合は、周辺に住宅が少なく、企業が多くなります。
オフィス街を歩いている人の大半は住民ではなく、サラリーマンなので、サラリーマンをターゲットにする必要が出てくるわけです。
その場合、例えば周辺企業を訪問して挨拶まわりをすることや、先に書いたようにMEO対策を含めた検索エンジン対策が有効になってきます。
サラリーマン向けにインフルエンザの予防接種や健康診断を安く行って、口コミを得るのも良いでしょう。
一方、駅からほど遠い地方都市のクリニックでは、近隣の住民が、車や自転車で来院することが考えられます。
そうなってくると、信号待ちの発生する交差点など、交通の要所に看板を設置するといった対策が有効だったりします。
地方都市の場合は検索エンジン対策が不十分な医院・クリニックが多く、早めに検索エンジン対策をしておくと、すぐに上位表示されます。特にMEO対策は効果がすぐに出てくると推測されます。
このように、どこで開業したかによって、集患・増患の戦略はかなり変わってきます。
立地条件に併せた集患・増患対策を考えるようにしていきましょう。
患者はめったに通う病院・クリニックを変えない

患者さんは滅多なことでは、通う病院・クリニックを変えようとしません。
例えば待ち時間が少ないなどの魅力や、普段通っているクリニックで不満がない限り、なかなかクリニックを変えないのです。
実際に、自分を振り返っても、周りを見渡しても、ずっと同じ病院やクリニックに通い続けることが多いのではないでしょうか?
そのため、近所に新しいクリニックを新規開業したとしても、なかなか患者さんが振り向かない可能性があります。
高齢者ほど、顕著にその傾向があります。
しかし、医療機関の診療圏がとても狭いという点もあります。
都心や全国主要都市の駅前で半径500m~1km程度、郊外や地方都市でも3~10km程度と言われています。
具合が悪いのに、わざわざ遠くの病院・クリニックには通いたくないのです。
つまり、この狭い診療圏のなかに競合となる病院・クリニックが少なければ大丈夫なこともあります。
物件の選定ではこれを意識して、新規開業した際は、診療圏は狭いということを認識したうえで、集患・増患対策をするといいでしょう。
医療機関同士が連携して地域医療を支える

ターゲットを絞り込み、医院・クリニックの専門性を高めていくメリットは競合を避けることだけではありません。
医院・クリニックの専門性を高めていくことで、近くの医院と連携することが可能になってくるからです。
つまり、近くの医院・クリニックは敵ではなく協力関係にあると考えて良いでしょう。
実際に、最近は近所の医療機関同士が上手に連携を図り、地域医療を支えているような例は増えています。
少子高齢化の影響で、全体的に患者数は増えています。総合病院では対応しきれないくらいになっています。
また、各診療分野の専門性が一段と上がり、1つの医院・クリニックで対応できる範囲に限界が生じてきています。
これは少子高齢化の日本では大きな課題になっているところですが、医院・クリニックにとっては連携のチャンスと言えます。
「思うように患者が来ない」という先生の悩みは、連携という形で解決できるかもしれません。
【まとめ】開業直後の集患・増患ができればその後軌道に乗る
以上、開業した医院の集患・増患の注意点について書きました。
- 病気にならないと医院には興味を持ってもらえない
- 患者さんは病院を探すときはネットで検索する
- SEO対策だけではなく、MEO対策も視野に入れる
- 立地によってマーケットの戦略は変わってくる
- 患者はめったに病院を変えないが、診療圏は狭い
- 近くのクリニックは敵ではなくて、協力関係
少子高齢化の加速で、医療機関のニーズは留まることはないと思います。
「思うように患者さんが来ない」とお悩みの開業医の方の大半は、単に患者さんに知られていないだけではないかもしれません。
連携などで解決するかもしれません。
どちらにしても、開業時に患者さんが最初から多いことは少なく、開業前の事業計画でも想定患者数は少なめに見積もることが多いです。
しかし、開業直後の集患ができるようになると、その後は患者さんが継続して通ってくれるようになります。
その後は、患者満足度を高めるようにすると経営は安定するでしょう。
こちらの記事も併せてご覧ください。


監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。